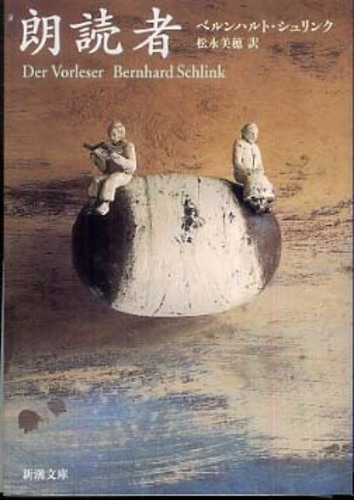要約
十五歳で黄疸にかかった主人公は約20歳年上のハンナと関係を持つ。彼らの日常は、朗読と、その後の情事が主だった。しかし、ハンナは突然彼の前から姿を消した。そして数年後に再開する、ナチス時代の戦争裁判の被告人と、その傍聴人として。ハンナはかつて収容所で看守をつとめていた。主人公は法学徒として「過去の再検討」について学んでいた。それまで学問として、俯瞰して学んでいた「過去の再検討」は、ハンナの裁判によって、自身の過去と向き合わされることとなる。
感想
裏表紙には「世界中を感動させた大ベストセラー」とあるが、物語の重さを受け止めるのに必死で、感動する暇がなかった。
本作には、観点が多い。
ハンナに注目するか、主人公に注目するか。あるいは、ハンナは字の読み書きができないこと、彼女がかつてナチスの収容所で看守として働いていたこと。主人公はそんな彼女のバックグラウンドを知らずに15歳のときに彼女を愛したこと。法学徒として、ポスト戦争の人間として、冷徹に俯瞰してナチス時代を考える一方で、当事者であるハンナを愛した自分もまた当事者としての何等かの責任があると考えること。
これらの要素が複雑に絡み合って、私の思考でデッドロックが発生する。ある視点で何かを考えれば、別の視点がそれを否定するような感覚に襲われる。
蓋し、ハンナにせよ、主人公にせよ、最後まで自身の本心に向き合えなかったように思う。ハンナは主人公からの手紙を待ち続けていた。主人公はハンナに愛していると伝えられなかった。
なぜできなかったのか。それは、先にあげた様々な環境的・時代的・個人的な要因があげられる。しかして、果たしてそれらが二人の関係の障害になる必要はあったのだろうか。
読者としての私は、二人にもっと我儘になってほしかったように思う。二人が我儘になれなかったのは、罪と責任が重くのしかかっていたからであり、決して優しさによるものではないだろう。しかし、社会や時代と切り離された、あくまで二人の関係においては、もっと我儘に互いを求めたって良かったのではないかと思わずにはいられない。
このように二人の葛藤や罪、責任の意識を考える時、私は何を考えればよいかわからなくなる。
本作が「世界中を感動させた」かどうかについては正直、疑問の余地があるように思う。しかし、本作が、人々の心に何らかの思考の種を植え付けるような感覚を与える点で、「大ベストセラー」と呼ばれることに異論はない。
余談
とはいえ、現代に生き、数々のエンタメ小説に毒されている私としては、本作は物語の展開が少し稚拙なように感じてしまった。
淡々と語られすぎている。
字の読み書きのできないハンナが主人公に向けて手紙を送ってきたときや、ハンナが自殺したときの描写は、もっとひきつけるように書けたのではないかと思ってしまう。
あまりにもあっさり書かれるものだから、よく意味を理解しないまま読み進め、数ページたってから事の重大さに気付き読み返すという事態になっていた。
この淡々とした回顧録的な書き方が本書の魅力であることは理解しているが、現代のエンタメを餌に生きる私としては、もう少し書きようがあったのではないかと思ってしまう。
この感覚は、大事にすべきなのだろうか。それとも作品に寄り添っていくべきなのだろうか。