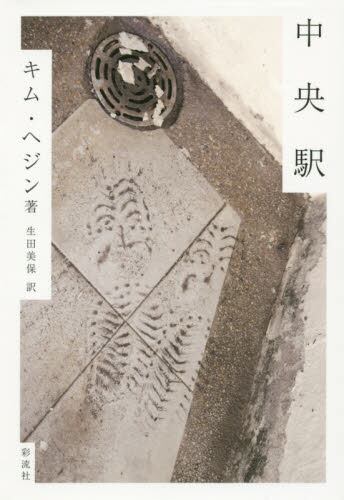感想
真っ先に思い出したのは、「死にたくなったら電話して(河出書房)/ 李龍徳」の存在である。どちらも、絶望のさらに底を突き詰めたところから見出せる人間の力強さを描いている。ただし、「死にたくなったら」の主人公が大学生であるのに対して、本作はホームレスであり、望む望まないを問わずにその境遇に落とされたという点で、「死にたくなったら」よりも切実である。
ただ、本作をそのようにして読んでよいのだろうか。つまり、究極の絶望の渦中であっても希望が存在「してしまう」ということを、本を読める環境にいる私が「作品として」素晴らしいと賞賛するのは、何かすごく大事なものを見落としてしまっているようにも感じてしまう。もちろん本作を読んだからといってボランティアに今すぐ申し込むべきというわけではないのだけれども、とはいえこの作品を受け止めるには、時間がかかるし時間をかけたほうが良いと思う。
また、この考えは解説や帯にて言及される「愛」においてより顕著になる。作中の二人の交わりが愛であったかどうかというよりも、既存の「愛」という枠組みに捉えて本作を語ろうとする姿勢自体がそもそも少し間違っているような気がする。彼らの交わしたものは、愛でもあり、愛に似た異なるものでもあり、到底既存の概念で語りきれるものではない。読み手と彼らの状況が大きく異なる点を考慮せずに、ただ単に「愛」と述べてしまうのは、やはり重大な何かを見落としてしまうのではないだろうか。
では、以上を踏まえて私は何を語ることができるのだろうか。結論は、不足した言葉と思考の中でそれでも語るしかないという陳腐なものになると思う。しかし、そうとしか思えない。本作の抉るような絶望は、本を読める環境にいる読者の心までも抉っていく。その抉られた痕を、簡単な言葉ですぐに塞ごうとするのでなく、しばらく眺めて、ヒリヒリする痛みを感じる時間が必要ではないかと思う。