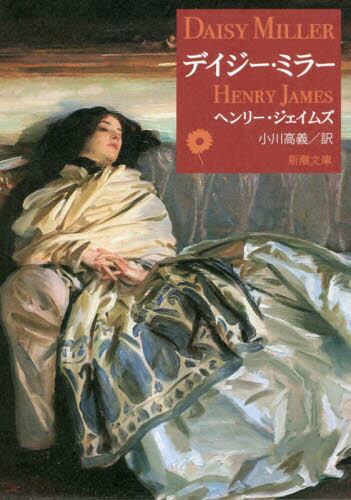感想
帯が許せない。帯が、本当に許せない。
帯には「誰が彼女を殺したのか?」と、大きく書かれている。なぜ、一体なぜ、物語の結末を帯でばらしてしまうのか。全くもって許せない。たとえヘンリー・ジェイムズが、発刊後すぐに海賊版を刷られるような有名な作家だとしても、ネタバレは絶対に許されない。
確かに、デイジーが亡くなる結末が本書の肝ではない。あくまで、なぜ・誰が・どうやって、彼女を死に至らしめたかが争点となる。直接的な死の原因は、マラリアだが、その道程を辿ると様々な遠因が見えてきて、考察のし甲斐がある。解説にて「心理主義的リアリズムを先導し」たと評されるだけのことはある。
とはいえ、とはいえ!物語として、デイジーが亡くなるのには、(ネタバレなしで読んだならば)大きな衝撃がある。奔放で天真爛漫な、およそ死とは結び付かない女性が、最後にはマラリアにかかってあっけなく没するのは、あまりにも唐突である。この読書体験を丸ごと損なってしまう本書の帯は、やはり度し難い。この帯を書いた人間が、現在は出版業界から撤退していることを祈りたい。
ここまでが、帯への怨嗟である。そしてここからが、本書の感想文である。とはいえ、ネタバレのせいであまり集中して読めなかったので薄い内容となる。
本書は、考察することを前提とするとすごく面白い本だと思う。解説に気付かされたが、登場人物のネーミングには人名を越えた意味が潜んでおり、多くの暗喩が登場する。こうした比喩や含意を一つ一つ発見し、丁寧に解釈していくことで、本書は何十倍もの奥行を持つことになる。
一方で、こういう作品は原書を読んでこそのようにも思える。訳者解説にてその苦悩が示されていたように、単語一つとっても、著者がその意味を考えて選んでいることがよくわかる。ゆえに、翻訳では著者の用意した意味が、訳者の意図の有無を問わず消えてしまう可能性がある。訳者解説を読んで、本書を面白く感じた一方で、原書で読みたいと強く感じた理由はここにある。
また、物語の中心となる人物(本書ではデイジー)を、傍観者に近い立場の人間(本書ではウィンターボーン)が解釈する視点で進行する物語は、「チェス奇譚(シュテファンツヴァイク)」を思い出す。時代としてはヘンリー・ジェイムズのほうが早いので、影響の有無を考えるとヘンリー→シュテファンだろうが、そもそも生まれた場所がかなり異なるので、シュテファンがヘンリーのことを知っていたかはわからない。いずれにせよ、誰かを解釈するというプロセスを追体験する小説は読んでいて楽しい。
醜悪な帯のせいで、読書感想文が2024年で1番長くなってしまった。実に不名誉なことである。しかし、作品自体に罪がないのはもちろんのこと、再読に耐えうる味わい深い作品だったのは間違いない。浅学非才ゆえ、ヘンリー・ジェイムズを全く知らず、これが初めてであったため、面白い作家を新たに知ることができたということで腹落ちさせるものとする。