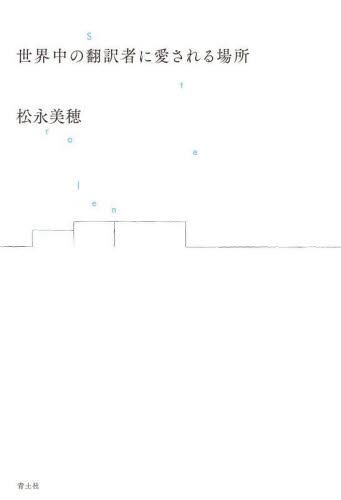感想
翻訳家になりたい、シュトラーレンに行くために、シュトラーレンで様々な翻訳家と出会うために、シュトラーレンの爽やかな空気で呼吸するために。これは決して比喩ではなく本心である。シュトラーレン、それから「翻訳家の家」はあまりに魅力的で、豊かな知性と翻訳への情熱に溢れているように感じられる。嗚呼、シュトラーレン、今すぐ行きたい、シュトラーレン、でも私はドイツ語話せない。
そもそも、私は今まで「翻訳家の姿」というものを考えたことがなかった。作家の場合は、あとがきや解説などでその境遇が語られ、どのような背景でその作品が書かれたのかまで説明されるが、翻訳家はむしろ逆で、良くも悪くも透明な存在である。本書で触れられた通り、国によっては表紙にさえ名前が載らない黒子のような存在で、彼(あれ)らが翻訳に従事する姿を思い描くことは難しいどころか、思い浮かぶことすらなかった。
しかし、(当然と言えば当然だが)翻訳作業の背景には、シュトラーレンのような光景が広がっていることだってあるのだ。これはもう、作家のことしか考えていない私の視野がいかに狭窄だったかを思い知らされるばかりである。ただその一方で、新たな景色が拓けるようでもあり、心持としては大変清々しい。もちろんシュトラーレンのような「すべてが緑の領域」で翻訳する方ばかりではないだろうが、翻訳に励む様子に思いを馳せることができるようになったのは、本書のおかげである。
それから、本書には著者の文章の癖が色濃く出ているのが良い。とにかく、端的なのだ。一文一文が短く、極めて冷静である。原書の雰囲気をいかにそのまま伝えるかが重視される訳文とは対照的に、訳者本人の文章は個性的であるため、読んでいるだけで面白い。実際のところどうかは置いておいて、著者個人の姿が浮かぶようで、黒子にしておくには勿体ないユーモアがある。
やっぱり、翻訳って、翻訳家って、面白い。著者もたびたび言及していたが、世界中の文学作品を読めるようにしてくれる翻訳家たちに、もっと敬意を払うべきだし、もっと関心を持たれるべきである。作品としては黒子であっても、翻訳家の中には様々な想いと熱意が満ちていることを教えてくれた素敵な一冊だった。