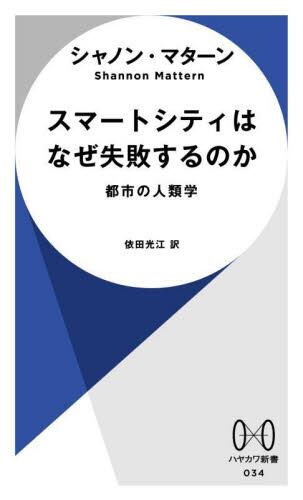感想
視座は面白いものの、主張がいささか極端なようにも思えてしまうのが正直なところ。スマートシティに対する視点がひとつ増えた一方で、本書を丸々肯定するには至らなかった。
まず、本書の主な主張は、スマートシティというまちづくりの過程で実施される「情報処理」によって抜け落ちてしまう要素が多分にあり、結果的に「まち」そのものを弱らせてしまうというものである。確かに、管理者が必要とする情報「だけ」を取捨選択して画面上に提示してくれるというのは、便利な一方で、知らず知らずのうちに視野が狭くなってしまう原因ともなる。スマートシティに限らず、我々が日常的に使用する「スマート」な機器に触れる際には、情報処理の過程で不必要だと判断されたものに目を向けられることが望ましいことが伺える。
一方で、本書で批難されている「情報処理」は完全な悪ではないとも思う。というのも、スマートシティに係る技術が集積してくる情報は、とにかく膨大で多岐にわたる。一人の人間が一生涯かけても分析しきれないほどの情報が、わずか数日で管理者やユーザのもとに集まってしまうのだ。したがって、機械による情報の取捨選択は、もはや現代において必要不可欠なものなのである。それを一方的に責め立てるのは、情報処理の恩恵を少し軽んじているのではないかと思えてしまう。
とはいえ、現代の情報処理技術に手放しで賛辞を送れるわけでもないのは、本書を読むことで実感できるため、蓋しバランス感覚が重要なのだろう。ChatGPTを始めとした生成AIの普及にも関連することだが、便利な機械やツールをただ使っているだけでは、いずれ機械に「使われて」しまいかねない。したがって、何かを利用する際には、裏側でどのような処理が走り、どのような取捨選択があって利用者に結果を表示しているのかを意識しなければならないといえる。
ここまでが本書の「内容」に関連する感想である。多少極端で、首を傾げる部分はあるものの、表題の惹きに劣らない興味深い内容だったと思う。が、しかし、本書は非常に、非常に読みづらい。例えば以下の文章である。何回読み返しても、すっと頭に入ってこないのは私だけなのだろうか(言わんとすることは理解できるけど)。
プランナーやプログラマーの協力のもと、設計チームはウェブや「モノのインターネット」の理想化したネットワーク構造を都市の形態に変換することを構想した。
p.92 第二章 都市はコンピューターではない
不遜ながら以下に代案を提示したい。
・設計チームは、WebやIoTが理想とする構造を、都市に変換することを構想した。
かなり勝手訳が入っていることも、そもそも私が原文を知らないことも承知の上だが、内容としてはこれでも問題はないと思うのだが、どうだろう。一応末尾に、代案の検討にあたって考えたこと、もとい言い訳を書いておく。原書を知らない以上、どの過程で読みにくい文章になったのかは定かではないが、我儘な一読者としては、もう少し手心があってほしかったと感じてしまう。
言い訳
1)プランナーやプログラマーの協力のもと
おそらく、直後に「プログラマーで技術系ライターのポール・マクフェドリーズはこう解説する。」と続くので、「構想した」人間の中にプログラマーが含まれていないと繋がりが悪いと判断されたのだろう。しかし、本書全体でIT系の話をしているので、別に当該の一文がなくても設計チームにポールが関わっているのは想像できる。何よりも長い。前提条件を飲み込むだけで苦労するような文章は、削るべきだろう。
2)「モノのインターネット」
「モノのインターネット」はコーパス(少納言)にない(IoTは95件該当)。ハヤカワ新書の翻訳メモリーとして仕方ないのかもしれないが、IoTのほうが1単語なので頭に入りやすく、妥当ではないだろうか。なお、「ウェブ」を「Web」としたのは「IoT」の記載に合わせた形(見やすさを考慮して)。
3)理想化した
コーパスによれば、「理想化した」が11件に対して、「理想とする」は109件である。私はコーパス原理主義者ではないが、「理想とする」でも通じる上、可読性が高くなるのでこちらのほうが良いのではないだろうか。
4)ネットワーク構造, 都市の形態
本文章において、「ネットワーク構造」である必要も、「都市の形態」である必要もなく、「構造」「都市」で十分理解できる。翻訳の都合上仕方ないのなら、できれば原書が出版される前段階で、編集者なりからツッコミが入ってほしかったと思う。