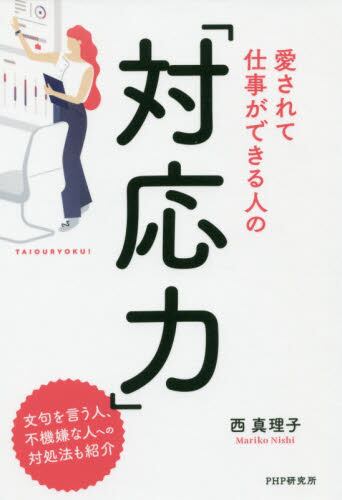感想
モテる人の「さしすせそ」を太字で書く本が、まさか令和元年に出版されていたとは思わなんだ。他のポイントも悉く凡庸で、Twitter(現X)でフォロワー千人規模の自称コンサルタントが毎日一つずつ呟いてそうな内容ばかりである。1冊読んで何も響かないというのは逆に珍しく、ある意味で新鮮な読書体験になった。
しかし、1点だけ心に留めておきたい言葉があった。「確認してください」という便利ワードを使いすぎるなという主張である。これには激しく首肯する。私自身、「確認してください」や「という認識です」などの汎用性のある言葉を乱用しがちである。これは、意図が正確に伝わらないのはもちろんのこと、語彙の減少によって言葉遣いが貧弱になっていくので楽しくない。
1年以上書き続けているこの読書感想文だって、ともすれば似たような表現が乱立することが少なくない。最近感じているところでは、「~だろう」「~ではないだろうか」という言い回しが頻発していることを気にしている。また、文末の調整も難しい。「~だ」「~である」「~いる」など、なるべく散らすようにはしているものの、意識しすぎて逆に違和感を覚えることもよくある。
加えて、感想文の構成も悩ましい。というのも、1年以上書いていると、概ねいくつかのおきまりパターンが生まれてくる。わかりやすい例だと、最初褒めておいて逆接で疑問点を挙げる構成や、反対に、始めは多少貶すもののそんなこと気にならないくらい良い作品であると持ち上げる構成などだ。読書感想文という大枠が前提として存在しているため、小説や日記ほど自由度がないのは仕方ないことではあるものの、もう少しバラエティーに富んだ話づくりをできるようになりたい。
話を戻すと、本書で心が動いたのは「便利な表現に甘えるな」というこの一点のみである。読者という立場で不遜なのは重々承知だが、それ以外は本当に驚くほどに凡庸なのだ。当たり前のことを当たり前にすることが難しいとか、そういうことすら言えないくらい陳腐で、読んだ内容はそっくりそのまま明日、いや1時間後には忘れているだろう。
しかし、読んだ甲斐は十分にあった。なぜなら、上述したような、文章を書く上での私の悩みをつらつらと書くまでに至ったからだ。たとえ99.9%がつまらなかったとしても、0.1%が私の心に引っかかり、それを基に何百、何千、何万という言葉を生み出していけるならば、それだけで十分儲けものである。本、特にビジネス書はそういうもので、砂漠の中から砂金を見つけるような作業が案外楽しかったりするのだ。