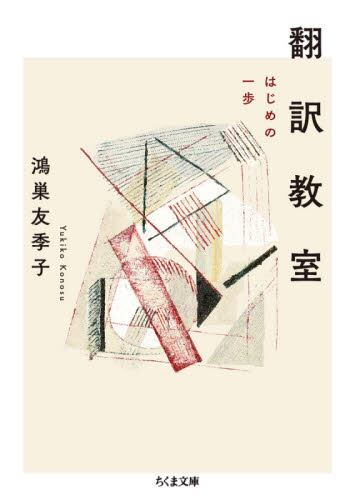感想
翻訳は、何かを読むための手段ではない。他者や他なる世界に深く沈んでいき、そこから見える景色を届けようともがく営みであり、人生を豊かにしてくれるかけがえのない存在である。それを、たっぷり余すところなく伝えてくれた一冊である。表題には「はじめの一歩」とあるが、その一歩はあまりにも大きく、あまりにも尊い。
と、ここまでは年始に読んだ「翻訳のレッスン(講談社)」で感じたこととそう変わりはないのだが、本書はその伝え方・構成が抜きんでている。第一に、翻訳の本なのに翻訳の話から始まらないところ、第二に翻訳に挑戦するのは小学六年生の児童だということが挙げられる。いずれにしても、翻訳・翻訳者のイメージからは離れたものであり、本への引力が強い。
まず、一つ目の「翻訳の本なのに翻訳の話から始まらない」についてだが、著者は小学生に対して、世田谷線になりきった作文を書くよう課題を出す。英文は一切出てこないどころか、「世田谷線になりきる」というかなり奇抜なテーマである。果たしてこの課題が翻訳にどう繋がるのかと訝しく思うのだが、すぐにその意味について気付かされる。
著者の言葉を借りるなら、翻訳に大切なのは「想像力の枠から出ようとする」ことだ。生まれも育ちも何もかもが異なる原作者の思考に寄り添うために必要な営みであり、それがこの「なりきり作文」に現れている。出生どころか無機物である世田谷線の視線を想像することで、自身の想像力の枠を打ち破ろうとするのだ。
実際、生徒の書いた文章には目を見張るところがある。感動さえする。鈴木るりか氏のような作家でもなければ、それよりも若い小学生の書いた文章でありながら、いやむしろだからこそ、柔軟な頭で想像力の枠を軽やかに飛び越えてまっすぐな作品を生み出せるのだろう。当然、彼らの作文の過程に苦労はあっただろうが、提出された作品には凝り固まったしこりのようなものが一切なく、とにかく自由で気持ちが良い。
このように、翻訳に必要な「想像力の枠から出ようとする」行為は、翻訳という枠組みさえも越えて視界の晴れる世界を映しだしてくれる。人間がいかに自分の常識に囚われて生活しているかということはよく聞くが、本当にそれを実感させてくれる経験は中々ない。そんな中で、翻訳という営為は、それを実践する人にも、読む人にも広大な視野を与えてくれる。翻訳が始まっていないのにも拘わらず、翻訳の本質を触れたように思う。これが本書の第一の良さである。
そして二つ目の「翻訳に挑戦するのは小学六年生の児童」については、既に一つ目でも触れたように、作家でもなんでもない、著者の母校ということで選ばれた区立小学校の六年生の年端もいかない若者が翻訳を実践している。対象作品は”The Missing Piece”で絵本ではあるが、それでも自身の小学六年生時代を思えばこそ、彼らには相当難易度の高い課題だと思えてならない。
ところが、あるいは当然のように、彼らはずんずんと力強く翻訳を進めていく。一言一句文字起こしされているわけではないので、当然ぶつかった障害は数多くあるだろうが、それでも、積極的に話し合いながら一語一語を訳していく姿は逞しく、知らん子供なのに親になった感動を覚えてしまう。おおきなったねえ……、おばちゃん泣いちゃうわ……。そういう心境である。
これだけでも十分素晴らしいのだが、成果物もまた唯一無二の輝きを放っているのだから驚きであり感涙ものである。”missing piece”を「驚きと喜び」へと翻訳をするのは、彼らが想像力の枠を飛び出しながら、作品世界の視点を獲得した結果に外ならず、ただの発想力では済まされない価値がある。翻訳という行為の尊さはもちろんのこと、それが誰にでも開かれているというところにも畏敬の念を覚えるのだ。
本当に、翻訳は良い。何度でも書くが、翻訳はただの商業的な営みではないし、ただ読まれるためだけに存在するのではない。想像力の枠を飛び越えた視点を獲得する道程こそが翻訳であり、それはむしろ、遍く人々のために存在していると言っても過言ではない。翻訳は、読むためでなく、するためにあり、決して廃れることのない大切な行為であることを本書は改めて実感させてくれた。最高でした。