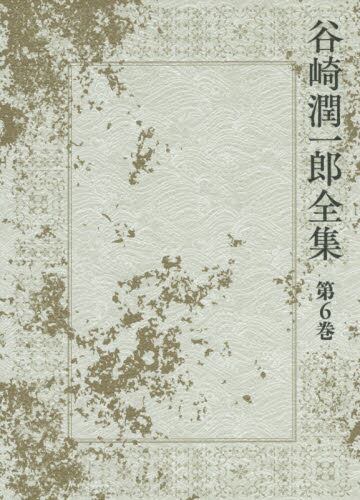感想
谷崎潤一郎の文庫を全て読み尽くし、全集の旅に出かけた第一歩である本作。文章そのものの良さを感じつつも、展開には物足りなさが残る結果となった。谷崎らしい文章でありながらも、谷崎らしからぬ展開であり、楽しいような残念なような少し複雑な心境である。
まず前者の文章そのものについてはもはや書くまでもない。だが、書く、語る。本作で顕著だった特長は、一つの文章だけで起承転結が存在しているということだ。たった一つの文章を読むだけでも、その前後で私の感情は大きく揺さぶられる。ダイナミックにうねる文章というのは、読むだけで楽しく、それが毎文なのだから余りある幸せである。文章読本を書くほど文章について熟慮に熟慮を重ねる彼だからこそ為せる技だろう。
また、本作では戯曲という形式で男女の会話が展開されるが、哀愁漂う味わい深さでありながらも、中々どうして軽やかである。戯曲である都合上、二人の周辺情報は最低限しか表現されないものの、むしろその情報の少なさによればこそ、たった二人の孤独な銀世界が一個の空間としてぼぉっと浮かぶようである。小劇場の舞台と、冬の森閑とした山中が融け合う情景は幻想的でありながらも、人間臭い親しさも感じられる。
こういった物語の雰囲気作りは、当然ながら文章力があってこそ実現されるものであり、並大抵の作家ではできないことである。谷崎の作品は一年ぶりとかなり久々に読んだこともあって、彼の文章を新鮮かつ安心感をもって楽しむことができた。
ただその一方で、物語の展開には少し物足りなさを感じてしまう。大まかな筋としては、劇作家である男性主人公が、良心の呵責に苛まれずに新たな妻と結婚するために、現在の妻を劇仕立てで殺害するというものである。そして実際、物語は台本の終了とともに幕を閉じる。
台本の中で台本が読まれるという複雑な構造は面白いのだが、とはいえクズな浮気男が自身の筋書き通り殺人を犯し、あまつさえ自己憐憫の末に自殺するだけのストーリーはかなり不快であり、カタルシスがない。痴人の愛や春琴抄のような、一癖も二癖もある女性を描く谷崎を知っている私にしてみれば、もっと複雑な、例えば玉子が佐々木に意趣返しをする展開を期待していたのだが、冒頭から宣言される結末に向かって真っ直ぐに進んでいってしまった。あまりにもひねりがなく、彼の著作の中では微妙である。
蓋し、谷崎作品というのは、愚かな男が強かな女性に虐げられるからこそ魅力的な作品になっているのではないだろうか。実際、愚かな男が立場の弱い女性を殺害する本作は、ただただ気分が悪く、耽美だとかデカダンだとかでは片づけられないつまらなさがある。
大正八年の作品とのことで、関西移住前であることから、私は本作が、まだ成熟しきっていない谷崎の習作だと解釈する。大作家にそんな評価を下すなんて毫釐も仮借されないことではあるが、これこそが著者本人以上に著者のことが大好きな強火厄介オタクの所以である。