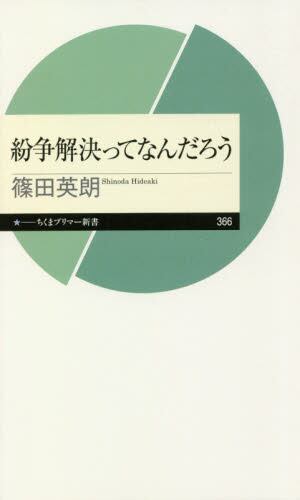感想
副読本、あるいは併読本が必要だと強く感じた。というのも本書は、種々の紛争から絞り出された様々なフレームワークを紹介している都合上、かなり抽象的なのだ。日本語自体は平易なのに、結局それが何を表しているのか具体的にイメージすることができず、字が滑っていってしまう。蓋し、具体的な事例を取り上げた書籍と併せて本書を読むことで、より解像度を上げてその事例を分析することができるのだろう。
ただ、正直それを抜きにしても読みにくいところがある。特に、語尾が揃っていることが多く、文章のリズム感が悪い。不思議な話だが、「~です。~です。~です。」と続くと、それだけで内容が右から左へ筒抜けになってしまう感覚がある。これは、有名な数々の文豪も苦戦していたものなので仕方のないことではあるが、とはいえ編集者さんや校閲さんのフォローが入ってほしかったようにも思う。
しかし、真っ向から批判できるかというとそうでもない。なぜなら、著者の誠実さが伝わってくるからだ。冒頭で多く語られるように、本書は日本では類例のない紛争解決学の教科書足りえ、かつ高校生でもわかるように書くという、非常に難易度の高い目標が設定されている。実際にその目標を達成されているかはともかくとして、文章からは妥協が一切感じられず、著者なりに全力を尽くして書きたいという想いが伝わってくる。
まあ、わかりやすく書こうとするあまり、まえがきではゲシュタルト崩壊を起こすほど「紛争」が登場するが、それとてご愛敬と思えるほどに、頑張って書かれているのがよくわかる。だからこそ、たとえ難しくとも、たとえ書かれてあることがイメージできなくとも、気持ちがくじけることはないし、内容に対して信頼を持てる。
今、私の机の上には、購入してから半年以上は放置されている「パレスチナ和平交渉の歴史」がある。私はこれを、本書とともに読んでみようと思う。おそらく、単体で読めばパレスチナの歴史をただただなぞるだけで終わってしまうところが、本書を併読することで、よりその構造に着目して、鋭く読み込むことができるのではないかと期待している。