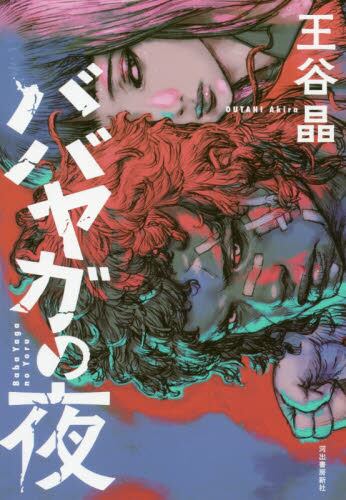感想
これは、やばい。ほんとうに、やばい。どえらい、やばい。
正真正銘の唯一無二。叙述トリックと、極道バイオレンスと、フェミニズムを全て兼ね備える小説なんて、後にも先にも本作だけではないだろうか。しかも、単行本にして180頁という短さの中でしっかりと様々な要素を束ね上げているのだ。著者の構想力と筆力に、ただただ感嘆するばかりか、もはや啞然としている。あんぐり開いた口が塞がらない。それほどまでに、本作はパワー溢れるものなのだ。
語れる箇所はいくらでもあるのだが、昨日「マリリン・トールド・ミー(河出書房新社)/ 山内マリコ」を読んだばかりなので、こちらと比較しつつ、ステレオタイプな女性性の解放について考えてみたい。血沸き肉躍る本作と、コロナで引き籠る「マリリン」では雰囲気が大きく異なるものの、似ている点もあるのだ。
それは、女性が逃亡している、という点である。ここで言う逃亡とは、逃避ではなくむしろ脱出に近い意味合いを持つ。「マリリン」の主人公は、性差別と格差のなくならない日本社会から脱出してオーストラリアへ向かうのに対し、本作では、極端な家父長制が支配するヘゲモニーな空間から、知り合いがおらず詮索されない社会へと脱出している。雰囲気の全く異なる二作において、ミソジニーの魔の手にはいずれも「闘争」ではなく「逃走」という手段を選んでいるのが興味深い。
これは単なる偶然ではないだろう。本作は2020年、「マリリン」は2024年に出版されたという点で、両作は2020年代のジェンダー社会を反映していると言っても決して過言ではないと思う。つまり、2020年代という今現在の段階では、個人レベルの性差別には逃走という手段での対抗が最も有効であり、かつ闘争・抵抗という手段では解決が難しい問題であることが伺える。
当然、「#MeToo運動」を契機に女性が声を上げるシーンが増えてきてはいるものの、それはあくまで集団での話であり、こと個人においては、当事者の置かれた環境や社会に拠って声を上げづらいと言えるのだろう。ウーマン・リブ自体は既に50年以上の歴史を持つものの、まだまだ社会には浸透していない、そう考えて差し支えないと思われる。
話を本作に戻す。上記のような個人での性差別に声を上げづらい中で、腐った男性を文字通り血祭りにする姿は、あまりにも爽快でありながら、単なるカタルシスに留まらない感動を覚える。女性を文字通り物にしようとする男たちの手をするりするりと抜けながら、顔面に拳骨を喰らわせて鼻っ柱をへし折る姿は、単なるアクション描写を越えた象徴として私の目には映ったのだ。
ただ一方で、最後の尚子の死は、物凄くやるせない気持ちになる。一応、亡くなったと明確に記述されていたわけではないので、いわゆる「読者の想像におまかせ」というやつなのだが、とはいえあの描写で生きていると考えるのは難しい。化物として積極的に暴力を振るってきた新道への報いなのかは定かではないが、正直、ご都合主義でも良いから二人が安心できる生活を見出す様子を描いてほしかったように思う。こういう血に塗れた作品にこそ、救いが欲しいんです……。
とはいえ本作は凄まじい。叙述トリックを利用した作品は普通、トリックそれ自体が話のメインディッシュになるのだが、本作はそんなところに甘んじたりしない。新道の喧嘩のように、作品そのものが強烈なエネルギーを充満させて、読者をぶんぶん振り回すのだ。そのため、グロテスクな描写が多分に含まれるのにも拘わらず、非常に爽快で、頁をめくる手が止まらない止まらない。
傑作と一口に言っても、色々な性質がある。何度も読み返してその価値を実感するスルメ的作品もあれば、重厚でボリューミーなステーキ的作品もある。一方本書に関しては、ただただ「圧倒的」である。何かに例える隙も与えてくれないほどに、圧倒的。文章に、物語に、文字通り打ちのめされるのだ。本当にすごい。本当にやばい。
文庫版感想
※250702追記
解説
うっま。お手本のような批評。イントロで突拍子もなくボクシングの話をしてから本題に繋げる鮮やかさ、男性としての主観的なバイアスを提示してから本作がそれにどう響いているか説明する整然さ、「破壊なくして創造なし」というぴったりハマる言葉を持ってくる巧さ、全てが過不足のない文章で、驚くばかり。
特に良かったのは、本作をよくあるフェミニズム小説としてではなく、「クラッシャー」として紹介したこと。フェミニズムや多様性という文脈で冷静に語ると、対岸の火事として受け流してしまう人が少なからずいるが、解説ではそうした安易なものにせず、誰もが必ず持つバイアスを「壊す」ものとして本作を位置付けている。そうすることで、本作は遍く人々が対象となっていることを示し、決して受け流せるものではないということを強調しているのだ。
いや~私も読書会で紹介したとき「クラッシャー」って言えば良かったなあ。フェミニズム的な側面について触れた瞬間、「あ~はいはいそんな感じね」って白けたやつがおったの、未だに腹立つ。そういうときは、フェミニズムよりもさらに大きな枠組みの、「バイアス」や「価値観」を「破壊」するものとして訴えかけるのが正しかったんやなあ。悔しい。
文庫版あとがき
暴力を書くのは気持ちいい。読むのも気持ちいい。みんなが気持ちいいからやってる。せめてそこに快感を感じているという自覚と後ろめたさは持つべきだなと思っている。
p.203
この人は相当信頼できる。上記引用を読んで強く感じた。
確かな事実として、暴力は気持ちの良いものなのである。そしてそう感じることが、決して悪いことではないのである。フィクションであれば、気持ちよく感じることでストレス発散にもなるし、良い気分になれる。しかし、そうした恩恵を受ける対価として、「自覚」と「後ろめたさ」が必要であると著者は言うのだ。
蓋し、この自覚の有無というのはものすごく重要である。言い方を変えれば自身を俯瞰で見ることができているかどうかという話で、それは暴力への傾倒のストッパーとなってくれるものでもある。行き過ぎた暴力がフィクションの枠組みを越えて本当に誰かを傷つけてしまわないよう、著者は暴力の功罪を意識することに努めているわけで、だからこそ本作の暴力は気持ちが良いし、気持ちよすぎることはないのだろう。