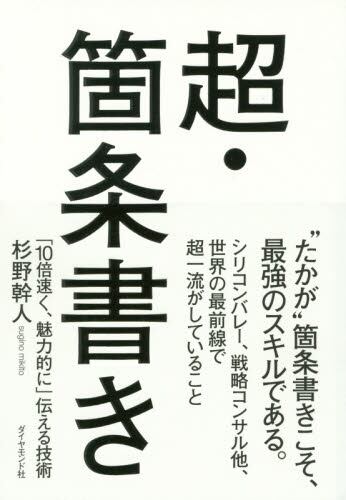感想
要旨
今までぼんやりと感じていたビジネス書と文芸書の違いに、今回ようやく言語化できるようになった。具体的には1)骨子か枝葉か 2)曖昧さ回避 である。当然、これら以外にもビジネス書と文芸書の違いはいくらでもあるだろうし、別ジャンルなのだからむしろ同じ・似た点のほうが少ないかもしれない。とはいえ、私は今までビジネス書と文芸書を同じ「本」という枠組みで捉えており、本書を読んでようやく、全く異なる存在だということを実感するに至ったのだ。
1)骨子か枝葉か
文芸では、どういった内容が書かれているかが非常に重要である。時代の先を行く内容や、その時代の価値観を根底から揺るがすような作品が、様々な賞を獲得したり、多くの人から評価を与えられる。例えば私が最近読んだ「ババヤガの夜」にせよ、「マリリン・トールド・ミー」にせよ、両作ともにそれまでそのような作品がなかったという点で共通している。このような作品は文芸評論家の間でしばしば「○○以前・○○以降」と表現される。このように、文芸というのは作品における新規性の占める割合がそれなりに多い存在なのだろう。
一方で、ビジネス書の内容はほとんど同じである。時代を問わず、国内外問わず、ほとんど同じような内容が語られている。例えば、本書でも度々登場する「MECE」というビジネス書ご愛好ワードや、「結論から先に言う」という言説である。また、本の構成も、何かができない・達成されないところから、できる・達成されるというステージへステップアップする進研ゼミ的な内容のものばかりで、文芸書で重視されるような新規性は全くない。
しかし、だからといってビジネス書が低級かつ低俗であると断じるのは勿体ない。なぜならビジネス書の骨子はむしろ、枝葉にあるからだ。というのも、ビジネス書では非常に多くの引用や具体例が用いられる。本書で言えば、「ジョブズのスピーチ」「ユニクロのプレゼン」「ソニー18箇条」「ドコモのスローガン」などである。ビジネス書は、陳腐な内容に説得力を持たせるためにこのような様々な具体例を持ち出す。本書に関しては正直有名どころばかりでつまらないが、ビジネス書の個性と面白さはこの「枝葉」部分にあるのではないだろうか。
2)曖昧さ回避
文芸書ではしばしば、「読者の想像におまかせ」という結末を迎える物語がある。中心人物の表情を敢えて描かなかったり、顛末を敢えて最後まで描ききらないことで、想像の余地を残し、作品世界に深みをもたらしているのだ。この「想像におまかせ」系は、現代においてはもはや王道の展開と言えるけれども、それでも読者の想像によって無限に世界が広がっていく様子を味わうのは楽しい。読書会に行ったり、人の感想をSNS等で眺める楽しさに共通しているようにも思える。
一方で、ビジネス書ではそんな曖昧さは言語道断、低評価まっしぐらである。先月読んだ「対応力」では、なんでもかんでも「確認する」と書く・言うのをやめろとあったが、本書でも「体言止めはやめろ」「改善する・見直すはやめろ」といった似た主張が為されている。ビジネス書は、文字通りビジネスのための書籍であり、ビジネスとはすなわち相手へ精確に伝えることに他ならないため、当然と言えば当然である。しかし、冒頭にも述べた通り、文芸書とビジネス書を同じ「本」というくくりで扱っていた私にとっては、この言語化によってようやくすっきりと切り分けられたように感じるのである。
まとめ
私はビジネス書をシニカルに見ていた。根拠のない肌感覚だが、小説を読む人間の中には、ビジネス書、あるいはビジネス書を読む人を馬鹿にする方が一定数いると思う。しかし、当然ながらそんな考えはお門違いも良いところである。なぜなら、そもそも小説とビジネス書では、楽しむポイントがまるで異なるからだ。既に述べたように、内容・枝葉という点や、曖昧さという点で、両者は正反対の面白さを持つ。だのに、私のような読者は無意識のうちにそれらを同列として扱うからこそ、一方を嘲笑してしまうのではないだろうか。
みんなちがってみんない。なんて陳腐な結論でしょう。でも、いかに陳腐な結論であっても、実感を伴って意識することは案外少ない。本書を通じて、なんとなく感じていたことを明確にし、実感をもって金子みすゞ的結論に辿りつけたのは、望外の良い経験だった。