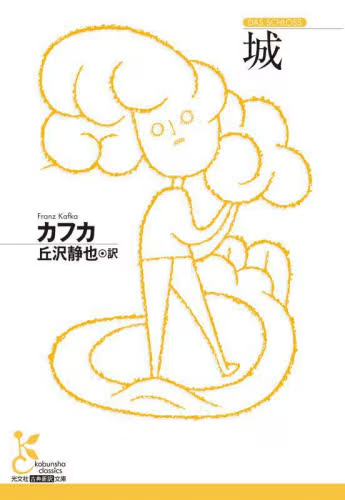感想
解説を読む前
読みきった達成感すら、虚しくしぼんでしまった。本作が初めてのカフカである私にとっては、とにかく冗長で、主人公Kの高慢さが鼻につき、それでいて物語が何も進展しないままばっさりと終わってしまう、あまりに甲斐のない作品だった。一応、仕事をしているのかしていないのかよくわからないお役所の実態のなさなど、世情を反映した名作っぽい雰囲気は感じられるものの、とはいえ個人的な好みで言えば微妙なところ。安部公房の「砂の女」を読んだときに抱いた感情と近いかもしれない。
そもそも、私は「未完」に対する心構えが甘かった。というのも、私は谷崎潤一郎の「乱菊物語」くらいしか未完の作品を読んだことがなく、未完というのはああいった打ち切りタイプのものだとばかり考えていた。ところが実際は、変なタイミングで割り込んでくるYouTubeの広告みたいな容赦のない終わり方で、「読み終える」ことを目標に、読むというよりもむしろ「耐え」ていた私はとんでもなく拍子抜けしてしまった。ゴールを目指していたはずが、そもそもゴールなんてなかったのである。
そんな感覚が抜けきらない状態でこれを書いているので、正直なところ内容について想いを馳せる余裕はあまりない。強いて印象に残ったとすれば、お役所仕事的な側面だろうか。役所へのたくさんの申請や、盥回しにされてどこからも正確な回答が得られない様子は、現代社会で働く私にも通じるところがあり、一向に実態の見えない「城」の存在はまさに、エンジニアにおける「客先」のように思えた。物理的に姿を見ることは叶わないし、やりとりをするにしても、プライマリやセカンダリといったメッセンジャーを挟まないといけず、一往復するにも時間がかかるというのは、IT時代だろうとなかろうと共通しているのかもしれない。
それでいて、アマーリアやKのように、自らの立場を断固として主張すれば村八分という制裁が待っている。あるいは、フリーダのように他者を利用しながら強かに生き抜く者もいる。こういう点でも、労組の組織率が年々減少し、声を上げるよりも転職したほうが良いと思える現代社会と通じる部分が少なからずあるのではないだろうか。Kの村も、私の生きる東京も、現状を甘んじて受け入れるか・そこから逃避するかの二者択一であり、「社会を含めて現状を改善しようとする」選択肢はないのである。
以上がざっくりした感想である。もう、これ以上書きたくない。ここ1週間くらいカフカに多くの時間を費やしていたのに、あんな終わり方は、残念だよ……。まあ、カフカにしてみればそんなん知っちゃこっちゃない話なわけで、たらたら不満を述べるのは不毛である。とはいえ、「変身」は、本作の内容を忘れないうちに読みたい。短くて読みやすそうだし、本作への理解の助けにもなってくれるのではないかと考えている。
とりあえず、お疲れ様でした!!!
解説を読んだあと
なるほどねえ……。
幸か不幸か、なんとなく、楽しみ方がわかった。どんなことが書かれてあるかよりも、どんなふうに書かれているかが重要な作家で、その筆跡を一文字一文字、栄養として取り込むようにじっくりと味わうと面白くなるのだと理解した。文章そのものの良さで展開していくからこそ、時代を越えた普遍性を獲得して、幅広く愛されるようになったのだろう。
ただ、途方もなく高くて分厚い言語の壁にぶち当たった気もする。というのも、翻訳の過程で、ドイツ語のワンセンテンスが、8つの日本語に分割されているのだ。しかも、本書の訳者は原作の雰囲気をなるべく忠実に再現しようとする志向性があるのにも拘わらずである。真に本作を味わうならば、ドイツ語で読むことが必須のように感じてしまったのは確かである。
一方で、邦訳が3作もあるのは素晴らしい。先にも書いたように光文社古典新訳での訳者は、原作の再現に拘っている方だが、これほど世界的に有名かつ未完なのであれば、大胆な翻訳がもっとあってもむしろ楽しいのではないだろうか。翻訳というより解釈になってしまうが、とはいえそもそも正解はないのだし、最も正解に近づくためにはドイツ語が必修なのである。であればいっそのことたくさんの解釈を生み出し、そこから新たなカフカの姿を浮かび上がらせるのも悪くないのではないだろうか。
それから最後に、訳者解説含めて本作に励まされた点を挙げて城の旅を終わりにしたいと思う。励まされた点、それは繰り返しを厭わないということである。訳者も触れているように、日本語は文中での繰り返しは避けられがちである。かく言う私も、読書感想文の中ではなるべく表現が被らないように適宜類語を探しながら書いている。
カフカはその逆を行くのである。冗長なまでに同じ表現を何度も何度も繰り返して使うのである。しかし、訳者はそれこそがカフカの魅力であると、語彙の貧しさこそがカフカの素晴らしさであると熱弁する。瀟洒な言葉遣いで着飾らなくても、洗練された文章力があれば、魅力的な作品は生まれるということである。
私はここに大きな肯定を垣間見た。それは、文章は、小説は、途方もなく自由だということである。少ない語彙で書けるからこそ立派であるとか、豊富な語彙があってこそ名作になるだとか、甲乙の話ではない。むしろそういう意味では、両極に途轍もない大作家がいるのだから決着のつけようがない(一方はもちろんカフカ、もう一方はシェイクスピア)。
真に大切なのは、どんな文章を書いても良いということである。カフカでも、シェイクスピアでも、かんそうでも、好きなように書き続けることで名作が生まれることもあるのだ。自分の文章に対して思い悩むことの多い物書きの端くれとしては、この上なく励まされる話である。読了直後はへとへとだったのに、なんだか今は不思議と心地よい。訳者の個性的な文体含めて、文章の自由さと豊かさを教えてくれた本作は、なんだかんだ、読めて良かったと思う。