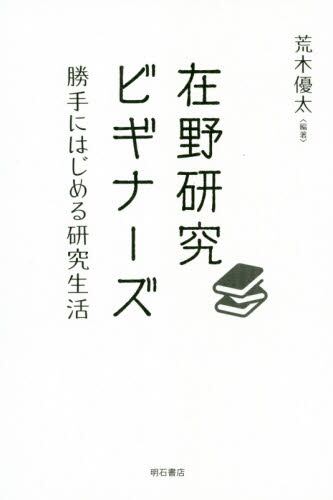感想
勉強と読書への意欲がもりもりと、もんりもんりと、もりりんもりりんと湧いてくる楽しい本。私の興味関心とは異なる分野を研究する方もままいるけれど、それでも読んでいて心が躍るのは、彼(あれ)らの登攀する道々が唯一無二で魅力的だからだろう。楽でないし、むしろ苦しさ満点かもしれないが、それでも精一杯研究に没頭する姿を読むのは気持ちが良い。
特に、一日の研究時間が28分だという、高校教諭を兼任する内田真木氏の話には驚かされたとともに、大きな勇気を与えてくれたように感じた。たとえ30分に満たない日々の研究でも、地道に粘り強く継続することで大きな成果を上げることができるのだ。塵も積もれば……と言えば陳腐だが、それでもそれを実践して突き進む様子はあまりにもかっこいいし、私も頑張ろうと切に思わせてくれる。
それから焦らないこともまた、凡庸ながら実感の籠った警句としてしばしば私の心に響いた。文芸評論の荒木優太氏は1年で原稿用紙40枚を、10年で400枚を書けばそれで本を出版できると書いている。私にとって10年とはものすごく長いタイムスパンであり、1、2年経過時点で早く成果を上げたいと思ってしまう。しかし、成果を急くことなく着実に積み上げ、それに奢らず何年も何十年も続けることこそが真の結果に繋がるのだろう。身につまされる思いである。
さて、それでは私も何か(例:小説を書く、韓国語・英語の勉強、韓国文学・フェミニズムの勉強・研究)頑張ろうと意気込んでみると、圧倒的なインプット量の足りなさに気づかされる。というのも、私は本をあまり「ブラウジング/総覧(p.73)」していない。それどころかその概念さえ念頭になかった。本サイトで読書感想文を書いている本は皆、頭から尻まで読み通したものであるが、このペースでは読める冊数に限りがある。図書館を活用して、とにかく幅広くとにかくたくさんの本と「ふれあう(≠読みきる)」ことも大事であると強く感じた。
何なら、そもそも私にはインプット量どころか資金も足りない。同好の士もいない。属するコミュニティもない。ないものだらけである。それでも、やるしかない。本書の研究者たちは、立ちはだかる障壁を飛び越えたり、迂回したり、方向転換をしながらなんとか成果をあげているのである。いや、むしろその縦横無尽な足跡にこそ、代えがたい価値が宿っているようにも思える。どこへ向かっているかわからなくても、どこかへ向かっているという事実だけを信じて、私もとりあえず頑張ってみようと思う。
余談
寄稿された研究者のほとんど全員が口をそろえて「インターネット最高!」と書いているのが面白い。
インターネットの恩恵について書かれてある記事や本は珍しくないものの、これほどまでに切な想いが、それもバックグラウンドの異なる14人+αの研究者によって語られるのは新鮮である。インターネットの普及に最も心を震わしたのは、テックギークでなくむしろ研究者のほうではないだろうか。