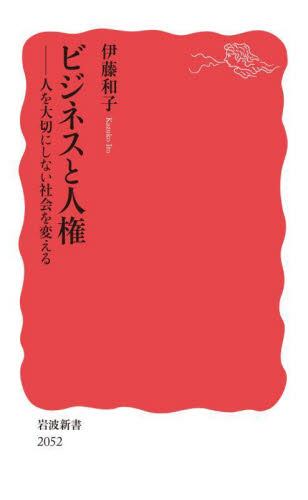感想
2024年時点での人権に関連する諸問題が包括的にまとめられていて、過去から未来へかけての中継地点のような一冊だった。地球環境というマクロな視点と、労働者個々人というミクロな視点までがバリューチェーンによって繋がっており、それらの問題が地続きで他人事ではないことを実感させてくれる。問題は大きいが、責任は組織のみならず各人にもあるのだ。
それにしても、日本の現状はあんまりにも劣悪ではないだろうか。単に私の無知が原因ではあるものの、ぼんやりと感じていた問題意識を遥かに凌駕する凄惨さである。特に、2024年の国連ビジネスと人権作業部会の報告書内にある、「日本が2023年に、児童労働を含む現代奴隷制のリスクがあるサプライチェーンからの輸入を通じた取引規模において、世界第二位であった(p.115)」ことには強く衝撃を受けた。なんとなく、日本と「奴隷」には縁遠さを感じていたからである。
蓋し、エシカル消費の大切さは理解していても、実践の優先順位は下がっていたように思う。稼ぎに余裕があるわけでない私にとっては、何をもってしても安さは正義だからだ。しかし、ここまでひどい惨状を目の当たりにすると話は変わってくる(ここまでひどくないと行動が変わらないのか?という問題は一旦置いておく)。私には、奴隷の身を強いられる人々の上に甘んじて恩恵を享受できるほどの図太さはない。様々な商品、特に、ファッションに関連するものを買う際にはそのサプライチェーンの在り方を調べるよう癖づけていきたい。
一方で、本書には少しだけ不満もある。べき論が多く、著者なりの提案がない点だ。本書には「○○をやるべき」「○○を実施しなければならない」という主張が多いのだが、それだけで企業が「わかりました実施します」となれば、そもそも今日に至るまで蔓延する人権問題は存在していない。当然かつ当然であってはいけないのだが、企業には「ビジネスと人権」問題に取り組むよりも、取り組まないほうが利益を多く獲得できるため、罰則にならない程度にしか取り組んでいないわけで、あれをやれこれをやれと主張するだけでは当然動いてくれない。
勿論、現状を報告して、読者それぞれが自身にできること、企業に対して主張できることを考えるよう訴えかけることは重要である。しかし、本書のように、2024年時点における人権問題を包括的に幅広く取りまとめて出版することのできる人間の視点には、一消費者の目には映らないものがあるのではないだろうか。専門家ならではの視座を踏まえて、解決の糸口を探る方法論も読んでみたかったように思う。
一応、本書内にそういう提案がなかったわけではないことは付しておく。企業に「責任」ではなく「義務」を科すべきという主張がそれである。そもそも現在の企業には「責任」までしか課せられていないことを知らなかった私にとっては、当然考えたこともない視点での提案だったので、新鮮かつ有用に感じた。とはいえ、利益の最大化が大きな目的である企業が、罰則という消極的な縛りによってのみでなく、自らが率先して取り組むような方策についてまで議論されていたらなお良かったように思う。
本書の歴史的なスコープはかなり短い。ビジネスと人権という概念は、誕生してからまだ20年も経っていないのである。だからこそ、ビジネスに蹂躙される人々が未だ数多く存在し、喫緊の対応が迫られている。個人レベルでは、エシカル消費を心掛けたい一方で、資本主義ゲーム内でいかに人権を上手く守れるかについても考えてみたいと思う。