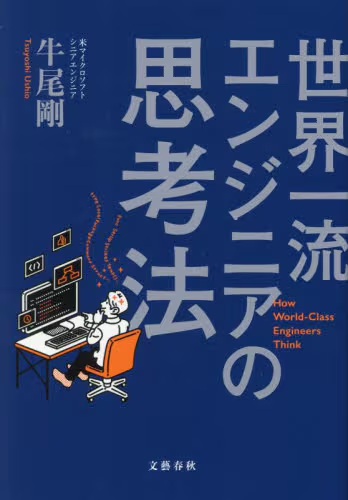感想
~ここはエンジニアの理想郷(ユートピア)~
表題の馬鹿らしさとは反対に、思想・実践の両面で多くの学びや気付きがあり、経験年数満2年のエンジニアにとっては大いに参考になった。すぐに始められる個人レベルの習慣から、将来リーダーやマネージャーになった際のマネジメントまで幅広く載っているので、定期的に読み返して参照したい(買う気になれないので、表題だけは本当にどうにかしてほしい……)。
中でも特に良い考えだと感じたものを3つ当感想文でも挙げておきたい。
1つ目は、理解と納得の違いである。著者は凄腕エンジニアの種々の習慣の大切さを「渡米前から言葉ではわかっているつもりだった(p.70)」と語るが、「実際に現地で働いてみると、想像の範囲を遥かに超えていた(同頁)」と振り返っている。これは本書の本質ではないだろうか。本書には、コペルニクス的転回を起こすような極めてドラスティックな主張は一切ない。しかし、それら全てを実践レベルにまで落とし込めている人は中々いないだろう。いかに頭で理解していたとしても、それらを実際的に納得していないと、結局は意味がないということであり、胸中に留めておきたい言葉である。
2つ目は、「自分が何も見ずにさくさくコーディングできるものを増やしていく(p.103)」こと。これはネットワークエンジニアにも共通する。何も見ずにコンフィグを打てるものを増やしていくことは、それだけ思考の余剰を生み、結果として「レベル4 自分だけでは解決が難しい(p.102)」問題にも余裕をもって取り組めるようになる。私自身、ミーハーで新しいもの好きなところがあるので、すぐ新技術について検証したくなるが、ぐっとこらえて、低レイヤのコンフィグを空で打てるレベルに引き上げることが、一流エンジニアへの、遠回りのようでいて近道なのだろう。
3つ目は、失敗を恐れないこと。何を今更という気持ちは、当然1つ目を読んでいれば封殺されるものとして、これについては著者のエピソードがとても印象的だったので取り上げたい。というのも、著者は「アメリカに来てから、失敗数は増えた(p.195)」と語っているのだ。なんて素晴らしいエピソードなのだろうと私は膝を打った。マイクロソフトに就職したからと言って、ステレオタイプなサクセスストーリーを歩むのでない。むしろ、より多くの失敗を経験するという、より泥臭い道程を歩んでいるのである。自身の美談を自慰のようにぶちまける粗悪なビジネス書とは一線を画す良さが、ここに詰まっていて、とにかく良い。
ここまで本書の良さについて取り上げてきたが、一方で懸念点もある。それは、果たして本書の内容を実践して生産性を上げられる日本の組織はどれだけいるのだろうか、ということである。
例えば、ほんの冒頭、第一章の第二段落には「全員がコンピュータサイエンスの知識があることが前提になっている」とあり、もはやこれが全てでは?とさえ思ってしまう。基礎知識をコモンセンスとしているからこそ、よりスムーズで建設的なコミュニケーションになるということは言うまでもない。未経験歓迎を掲げる多くの日本のIT企業からしてみれば、夢のまた夢で、気が遠くなる話である。
それに、「『仕事を楽しんでいるか?』と確認する文化(p.175)」が日本に根差すにも、2、30年くらいかかりそうである。今の4、50代、いや30代の人でさえも、残業時間を自慢することが少なくない。残業時間を勲章や善意のように捉える人が、もうほんと、どれだけ多いことか。そしてそういう人々は、残業を悪だと認めると、これまでの残業人生そのものを否定しかねないため、よほど出来た人間でない限りは価値観を受け入れ・変化させることはない。となれば結局彼らの勇退を待つより他なく、「仕事を楽しむ」企業の広がりはまだまだ遠そうである。
このように、本書の提案と、現実の日本の組織にはマリアナ海溝よりも深くて暗い隔たりがある。しかし、それでも腐らずに読み進められる魅力が本書にはある。
著者の筆がとにかく楽しげなのだ。コラム「海外のテック企業に就職するには(p.128-130)」が顕著で、著者はマイクロソフトでのエンジニア生活を心から満喫している。熟考しなくても自然と発露する明るさが、文章のそこかしこから感じられるのである。このポジティブな筆運びが、読者との隔たりを軽快に飛び越えて理想郷(ユートピア)たるエンジニア生活の幸福を、ひと時でも感じさせてくれる。
既に挙げた通り、本書には学びや気付きが多いのだが、それ以上に読んでいて元気になれる無邪気さに心を惹かれる。ビジネス書には珍しく、高圧的でもなければへりくだるわけでもない、等身大でピュアな感情がそこにある。どんな学びよりも、どんな隔たりよりも、その純粋無垢な心が、私に頑張ろうと思わせてくれたのだ。だからこそ、だからこそ、ただもう本当に表題のセンスが惜しい……。そんなコテコテでなくてもええやん……。