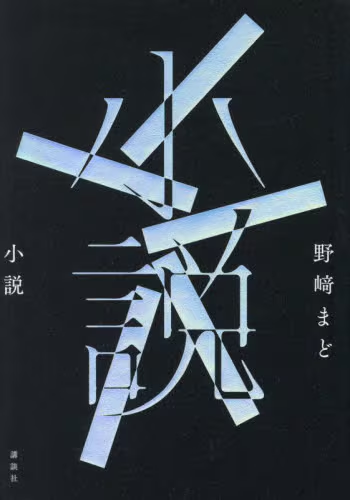感想
読みながら考えていた感想文の内容が、吹き飛ばされて、情緒がぐちゃぐちゃになっている。何から語れば良いかわからない。でも、良かったことだけは確かである。涙が出るほどに、良かった。内海的には、わざわざ言葉にする必要はないものの、私はそれを語りたい。本書を読んだ瞬間に感じたあれこれを、忘れないうちに、書き留めておきたい。
まずは何よりも、内海の変化が心に来る。彼の外側は、種々の出来事の前後で何も変わっていない。書店で下っ端として働き、小説を読むだけの生活は今までもこれからも続いていく。しかし、彼の内側は確実に変わった。書きもせずただひたすら読むだけの人生への迷いが吹っ切れ、それを肯定できるようになったのだ。
陳腐な結論になってしまうが、結局のところどんな人生であれ、当人がそれを肯定できるか否かで輝きが変わってくる。内海のような、バイトと読書以外何もない生活でも、本人がそれを良し、幸福に感じているならそれが全てなのである。そしてそれは、内海に限った話ではない。小説を読む者、即ち本書読者全員に向けて、小説を読む行為を肯定しているのである。外崎から内海への愛は、著者から読者への愛でもあるのだ。こんな圧倒的な肯定を読んで、涙せずにいられるだろうか。
それから、本作には個人的に思い出すものが多いのも情緒がぐちゃぐちゃの原因である。
まず、内海と外崎の関係は「おやすみプンプン(小学館)/浅野いにお」の清水と関を思わせる。清水と関が最後までディスコミュニケーションだったのに対し、タイムリープして再開を果たしたという点でこちらのほうが救いはあるのだが、互いを想いつつもそれが素直に発露しないという様子は共通していて、ある種いじらしい。純度の高いBLを読んでいる気分である(当然、ここで言うLOVEは、恋愛に限った話ではない)。
次に、外崎=髭先生という種明かしが、「一億年のテレスコープ(早川書房)/ 春暮康一」の顛末と似ていて、とにかく悔しい。「一億年」でそれはもう度肝を抜かれたのに、実はそれがネタ被りするほど有名な手法だったというのが悔しいのだ。要は無知ゆえに都合よく作品たちに踊らされたわけで、楽しいのは事実としてあるのだが、それはそれとして自身の無知が悔しい。もっとしたり顔で読んでやりたかったと、ちょっとだけ思ってしまうのだ。
そして最終盤になって語られる、小説を読むことで「内側を広げていく」という話は、(たしか)四畳半神話大系のワンシーンにもある。四畳半に引き籠る主人公は、自身の世界を外界ではなく内へ内へと広げていくのだ。作品中ごろで外崎が応募する長編小説新人賞の審査員に森見登美彦がいたことも決して偶然ではなく、ある意味この時点で「小説を読むことの意味」への回答は仄めかされていたのかもしれない。
ここまで一息に書いてきた。既に、本作を読んだ”瞬間”の興奮は冷めつつある。先ほど見た輝きは、もうおぼろげになっている。しかし、私は確かに見た。小説という星が、その星々に魅せられた人々の輝きが紙面から飛び出してくる様を確かに目撃したのだ。文字という嘘の中に、肯定という一筋の真実があったのである。
たぶん、これを読み返す時、相当熱に浮かされていたんだなと私は鼻で笑うだろう。それは仕方ない。しかし、本書に存在する圧倒的な肯定を読んだときの涙だけは、きっとこの先も忘れることはないだろう。仮に忘れたとしても、「肯定」という感情そのものだけは、私の心に残り続けるだろう。
余談
実は、思い出していたものがもう一つある。「TENET」だ。決定論の描写が、当映画での言葉遣いに似ていたというだけなので、感想文の中には入れなかったが、おそらく著者は観たのではないだろうか。単に私の中でTENETが強く印象に残っていただけかもしれないが。