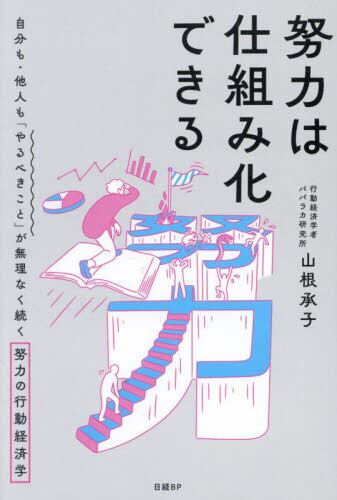感想
例えば面白いのは、低所得であっても、内的統制の強い人はあまり不幸を感じていないという研究です。
p.144 第3部・第6章
結局のところ、これが全てではないだろうか。本書は、行動経済学的アプローチでなぜ努力ができないかを分析し、その結果を踏まえてどのように仕組化していくかを論じている。しかし、本書でも触れられるように、努力は主観的なものであり、必ず結実するとは限らない。そのため、努力の有無を問わず幸せに感じられる在り方を模索するほうがよっぽど建設的である。そういう意味で、本書の論旨とは関係なく、上記箇所が本質のように感じられた。
とはいえ、この内的統制の強さが自己責任論を喚起しそうで、少し危うさを覚えるところもある。ステレオタイプな人間の見方ではあるが、人は、自身の常識を他者にも当てはめてしまいがちである。内的統制が高く、自分の人生は自分でコントロールしていけると思っている。つまり人生の責任の所在を自身に感じている人は、それを他者にも当てはめて、当人の不幸は当人の責任であると言いかねないのだ。当然、そういう人が全てではないものの、ある種の自戒として私の胸中に留めておきたい話である。
かなり話が逸れてしまった。とはいえ、本書に対して思うところはそんなに多くない。仕組化の手法については何一つ目新しいものはないし、それどころか取り上げられる研究の数値的な結果が、とても有意なものには思えず閉口してしまう。ほんの数パーセントの誤差みたいな結果を根拠に主張をしても良いものなのだろうか。グラフの縮尺を極端にズームインしていないだけマシだけれども、とはいえあまり説得力のある内容には思えない。
結局のところ努力は、環境と、心の持ちようである。過去・現在・未来の自分を客観的に分析し、何をすべきか・どうすべきか・環境を変えるべきなのかを考えて実行する。結果が出れば喜び次へ、出なければ反省して次へ。それをただひたすらコツコツと積み重ねていくだけである。銀の弾丸は当然ないし、そもそも死ぬまで結果は出ないかもしれない。だから、今この瞬間の人生を最大限幸福でいるよう努めることこそが大事なのだろう。我ながら、あまりにも月並みでつまらないが、本書から得られた実感としてはこんなものである。