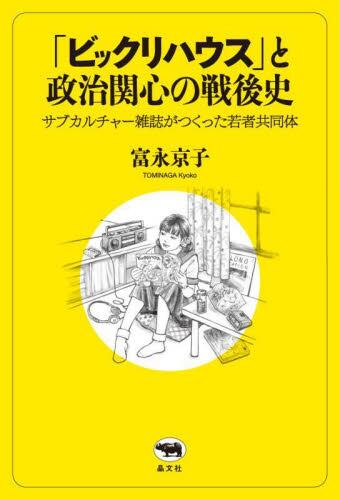感想
はじめに
面白くない。面白そうな雰囲気(装丁、値段、出版社、テーマ)は十分すぎるほどあるのに、それを凌駕するつまらなさ。ある意味で、期待値がマイナスからスタートするビジネス書よりもタチが悪い。では、一体何が面白くなかったのか。以降では、1)文章の薄さ 2)意外性のなさ 3)分析の稚拙さ の観点から語っていくものとする。
1)文章の薄さ
どの章を読んでも、一切代わり映えのしない内容である。毎章・毎部、「ビックリハウスのような『しらけ世代』は政治への志向・反発というパラメータでなく、新奇性によってアイデンティティを確立し、読者投稿という共同参加可能なコミュニティによって個性を確固たるものにしていった」ということしか書かれていない。この言説への反論など微塵もなく、あるとすれば、「そうとも言いきれない」と触れる程度の、浅い逆張り意識のみである。
そしてあろうことか、この内容の薄さに著者自身気付いているのだからやるせない。104頁では、「かなりしつこいようだが」と前置きして、それまでに散々ぱら話してきた内容を改めて繰り返している。「かなりしつこい」自覚があるのならば、校正の段階でより充実した内容に修正していただきたい次第である。
2)意外性のなさ
上述した通り中身が薄いにも拘らず、本書の内容には意外性が全くない。全共闘時代を白けた目で見てきた世代が中心となって、「おもしろ」を最優先に誌面で遊ぶ「ビックリハウス」は、それまでの研究が示す通り、同時代の他の雑誌よりも政治的な志向性が低い。ここに異議を唱えてドラスティックな主張をするかと思えばそうでもなく、ただただビックリハウスの政治性の低さを確かめていくだけなのである。
要は徹頭徹尾、「まあそうだろうね」なのだ。「へぇ~」という感嘆は一度も出てこず、抵抗もなく腑に落ちる内容がひたすら続くだけである。これをつまらないと言わずに何であろうか。やおい(ヤマなしオチなし意味なし)でさえ味わい深さはあるというのに、本書にはそれすらない。著者がビックリハウス世代でもないからノスタルジーさえなく、ただただ事実の列挙を眺めていくだけであり、何らかの景色でも眺めていたほうがよっぽど良い経験だと言える。
3)分析の稚拙さ
奇を衒ってか、共起ネットワークによる分析を行っているけれども、あってもなくても変わらない程の拙劣さである。有意差さえ示されず、数字の増減のみを指標にして傾向を分析しているのはお粗末も良いところで、あの図から一体何を見出せると言うのだろうか。
そもそも、共起ネットワークが用いられるのは「戦争」というごく1トピックだけであり、他のトピックでは、ただ言葉の登場頻度を数えただけでである。せめて各トピックで共起ネットワークによる分析を行ってくれないだろうか。集計結果があまり芳しくなかったのか知らないが、特定のトピックにだけ登場すると、分析結果ありきで分析手法を都合よく利用しているように思えてしまうのである。
まとめ
本書は本当に面白くなかった。この感想文を書くのでさえ、相当な苦痛だった。当然、研究なのだからわかりやすい面白さを売りにしてはいないだろう。とはいえ、2,500円(税別)もする、決して安くはない本なのだから、広義の意味で面白くあってほしいと願うのは、読者として傲慢だろうか。少なくとも私は、本書を新刊として買ったことを激しく後悔している。本書を買うくらいなら、岩波新書を2、3冊買った方がよっぽど有意義だっただろう。