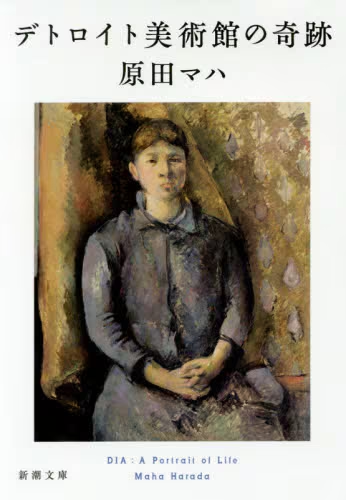感想
市の財政危機によって存続の危機に陥る美術館が、アートを愛する人々の想いによって市から独立して生き続けるという話。
予定調和で、驚きも感動もなかった。せめて長編として2、3倍の長さで重厚に書いてくれたのなら、また違った感想になるかもしれなかったが、実際は上述の通り1行で要約できてしまうほどの味気なさで、大きな山場もなくあっさりと読み終えてしまった。帯の推薦文では「映画になるようなワクワクするストーリー」とあるが、本作のストーリーはむしろ24時間テレビで重宝されるのではないだろうか。
加えて、第一章フレッドの話は、ステレオタイプなジェンダー観が強く、中々物語に入り込むことができなかった。本作の初出は2016年であるので、当然2025年現在の価値観とは異なるだろうけれども、とはいえ、例えばウーマンリブは1960年代からの運動であるわけで、「家父長制下での献身的な妻像」は2016年でも陳腐ではないだろうか。
まあ、小説を味わう舌が肥えているのは否めない。特に今年は、個人的に傑作と感じる作品が多く、豊作の年なので余計にである。翻って、二転三転どころか、一転すらしない本作のストーリーには惹かれるところが一つもなく、なんとも残念な心持ちである。
一方で、鈴木京香氏との対談では、著者の想いの一端を垣間見ることができた。「私は自分の小説は、アートへのいい入り口であってほしいと思っています。また同時にいい出口であってほしい。」という言葉での「いい出口であってほしい」というところがかなり示唆的である。著者としては、アートに興味を持ってほしいと思う一方で、著者の小説で満足してほしくないという想いもあるのだろう。小説はあくまで文字メディアであり、実際の芸術作品とは絶対に相容れない要素がある。そういう意味で、本作はアートへの入り口であっても、決して行き止まりにはならないのだろう。
実際本作にしても、物語としての面白さは皆無だが、デトロイト美術館への入り口として最適だとは思う。フレスコ壁画の「デトロイトの産業」を始めとして、種々の美術品は、著者の叙述を通して読者の目に魅力的に映る。加えて、美術館そのものが一度存続の危機を乗り越えたという歴史があるので、そうした背景を踏まえて行ってみれば、より深い感慨を得られるのだろう。
以上、本作は小説としてはありきたりも良いところだが、著者の持ち味である、美術への造詣の深さはいつも通り活かされている作品だった。