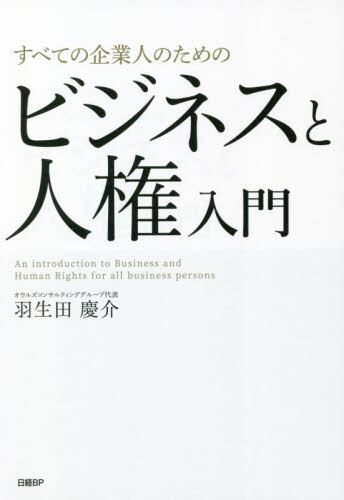感想
以前読んだ「ビジネスと人権(岩波新書)/ 伊藤和子」(以下:岩波版)で生じた疑問を解消し、その上で新たな視点を与えてくれた本だった。というのも、岩波版の読書感想文にて、「本書には『○○をやるべき』『○○を実施しなければならない』という主張が多いのだが、それだけで企業が『わかりました実施します』となれば、そもそも今日に至るまで蔓延する人権問題は存在していない。」と書いたのだが、本書では「べき論」から一歩踏み込んだ議論を展開しているのである。
結論を先取りすると、「新たな市場や事業を創出する視点(p.196)」を取り入れることこそが、「ビジネスと人権」の浸透に繋がるのだと本書は主張している。環境問題へのルール形成によって環境ビジネスが100兆を超える一大ビジネスへと拡大したように、人権問題もまた、近年になって様々なルールが形成されつつあるため、人権ビジネスには大きな将来性があると言うのだ。
恥ずかしながら私には、人権ビジネスという視点が全く存在していなかったので、この主張にはいたく感動した。企業が利益を最優先に行動するのならば、人権が利益に繋がるということを訴求すれば良いという発想の転換は素晴らしく、岩波版よりも明るい展望が垣間見えたような気がする。実利を優先しただけで意識は変わっていないという反論もあり得そうだが、黎明期にはまず新しいルールを広く行き渡らせることのほうが重要なので、本書の提案は少なからず有効だと思う。
加えて、そもそも旧時代的な働き方が生産的でないと、データを用いて主張しているところも素晴らしい。「韓国、男子(みすず書房)/ チョ・テソプ」が、ヘゲモニックな男性性なんてそもそも存在しないと論じたように、働けば働くほど生産性が上がるというステレオタイプな価値観もまた、無根拠な幻想なのである。多くの経営者にとって、人権意識を指摘されるより、生産性の悪さを責められるほうが苦しいのではないだろうか。
このように、本書は「ビジネスと人権」の普及に大きく貢献ができる本である。ビジネス書というジャンル含めて、普段専門書をあまりに読まない人にも訴求でき、かつ、人権意識の低い人に対しても、実利という点でアピールしていくことが可能なのだ。まさに「すべての企業人のためのビジネスと人権入門」であり、その表題に偽りなしである。
余談
本書には。失敗を糧に人権対応の先進企業と評される会社がいくつか登場する。ANAやナイキがその代表例だ。
こと2025年の現在において、果たしてそのような企業が生まれることはあるのだろうか。というのも、昨今のSNSは、一度炎上したが最後、骨すら残らないほど燃やされるのだ。そんな状況で、一度の失敗を糧に成長できる企業があるのか疑問に思う。
もちろん、そもそも炎上するなという話である。人権問題が起きうる状況を保持する企業がのうのうと事業を続けられるほうが良くない。そこに反論の余地はない。とはいえ、セカンドチャンスの機会すら与えないほどメタメタにするのは、どうなんだろうと思ってしまう。
まあ、起こした問題の大きさにもよるので、場合によりけりが結論な気がする。万引き(窃盗罪)なら、セカンドチャンスの余地は多少あるだろうが、殺人はどうしたってアウトである。人権問題も全く同じで、「オフセット不可」を踏まえて判断するべきなのだろう。