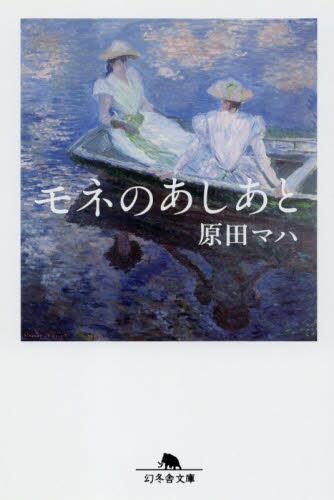感想
モネ周辺の印象派の歴史が概略的にまとまっており、大枠を掴むにはもってこいの一冊。「デトロイト美術館の奇跡(新潮社)/ 原田マハ」にて著者が自著に対して、「アートへのいい入り口で」あり、「出口であってほしい」と述べていた言葉がそのまま当てはまる。本書は専門書ではないものの、素人がざっくりとした概観を掴むにはちょうど良く、著者の小説群の副読本にもなってくれる。
と、本書の9割を読み終えたところまでは、おおよそ上記のような感想文を書こうと考えていた。ところがあとがきの「花は咲いている」を読んで、本書への印象がガラリと変わった。というのも、本書はコロナ禍のもとに書かれ、出版されているのだ。
著者は当時フランスでロックダウンを経験しており、その際にオランジュリー美術館での展示室のバーチャルツアーの様子を振り返っている。モネの睡蓮を見て、「私の奥深いところにそっと触れ(p.144)」、涙するのだ。そしてその涙を、「希望の涙だ(同頁)」と考えている。
ここに、現代で美術を鑑賞する一つの意義が存在しているように思う。高画質のカメラがスマートフォンに搭載され、インターネットを通じて世界中の人々の描く絵を見ることのできる世界において、それでもなお100年以上前の印象派芸術を鑑賞する理由は、そこに確固たる「感情」が宿っているからだろう。著者が希望の涙を流した理由はまさに、睡蓮の池に宿るモネの感情を垣間見たからではないだろうか。
確かにそういう経験は私にもある。ムンクの「太陽」と、ギュスターヴ・ロワゾーの「グルノーブルから望むモンブラン」で、圧倒的な生命力を感じたことがあるのだ。そしてそれは、ムンクやロワゾーが現地で持った感情が、作品の中にこめられており、鑑賞者に向けて解放されるからこそ感じられるものなのだろう。いずれも東京で鑑賞したが、都会では味わえない心地良さが、確かにあったのである。
話を本書に戻すと、コロナ禍で家に閉じこもらねばならなかったときにこそ、SNSで人と繋がるのでなく、芸術を鑑賞して「感情に触れる」ことが救いになったのだろう。誰が発したか忘れたが(※)、絵画は窓であるという言葉がある。まさにその通りで、絵画は自身とは異なる、「感情を持った」世界を繋ぐ窓なのだろう。そういう意味で本書は、印象派の概説的な本でもありながら、鑑賞する意義についてまで想いを馳せられる一冊だった。
※建築家のレオン・バッティスタ・アルベルティ。ただ、彼の文脈は、私の感想文の中で使った意味とは微妙に異なりそう。