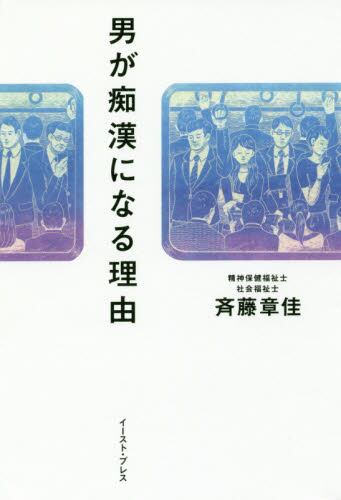感想
今現在、各所で行われている痴漢対策がどれだけ的外れで、付け焼き刃なのかがよくわかる本だった。本書は2017年に出版されたはずなのに、8年経った2025年に読んでも全く褪せておらず、私自身、いかに痴漢への理解がないかを痛感した。認識と実態が乖離することは性犯罪に限らず、あらゆる事象で起こりうるが、こと痴漢に関してはそれが顕著に感じたのである。
特に、私が衝撃を受けたのは、「ひとりの受刑者に年間300万円程度の予算が割かれる(p.197)」ということだ。新卒の手取りか、それ以上のお金が受刑者のために費やされており、実際に受刑者が受け取るお金ではないにせよ、莫大な額であることには間違いない。痴漢の検挙率を上げるとともに、痴漢、ひいては性犯罪がそもそも起こらない社会についても考えなければならないと強く感じた次第である。
この、「性犯罪が起こらない社会」のためには、実際の加害者のみならず、周囲の人間、特に男性の意識が変わる必要があるのは言うまでもない。本書でも取り上げられていたように、痴漢が起きても無関心を決め込むどころか、過度に冤罪を恐れたり、被害者へのセカンドレイプを行う者も存在する。加害者だけでなく、社会の人々のほとんどが、多かれ少なかれ痴漢に対して認知の歪みを抱えているのだ。
ここで私が感じたのは、加害者以上に、社会が内包する認知の歪みを変えるほうが難しいのではないかということだ。というのも、加害者には更生のためのプログラムが組まれ、様々な人からのサポートが受けられるが、社会にそうしたプログラムはない。加害者でさえ、プログラムを通して、十年以上の歳月をかけてようやっと変われるのに、そのような取り組みのない現在の社会が変わることはあるのだろうか。
正直、今の私はすぐに答えを出すことができない。事の深刻さを、本書を読んで理解したばかりだからだ。ただ、一つヒントになるのは「『いまの発言をどう思うか』と問いを投げ(p.240)」ることだと思う。認知の歪みは、本人が自力で気づかなければ、変容に至ることは難しい。だからこそ、相手へ内省を促すような声かけが重要になるのだろう。
そしてそれは、自身に対しても同様である。言い合いをしたときや、些細であっても心がざらついたときなどに、「いまの発言をどう思うか」と自身に問いかけることで、認知の歪みに多少なりとも自ら気づくことができるのではないだろうか。始めは変容にまで繋がらなかったとしても、継続することで、他者への共感やエンパシーに繋がり、社会の在り方を見つめなおす眼差しになると思う。
とかく痴漢は許しがたい。しかし、だからこそ、その行為に至ってしまうプロセスを理解しなければ、安心できる社会は実現しないのだろう。中々答えが出ないのは当然だし、明確で絶対的な答えはないだろうが、痴漢のない社会の実現については、継続して考えていきたい。