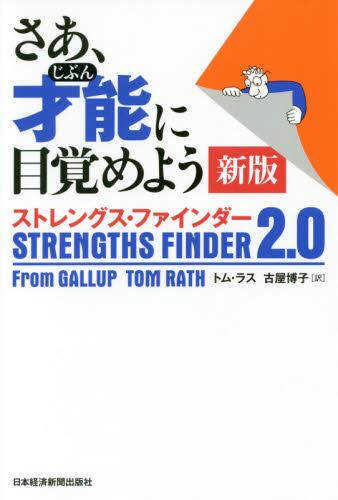
ストレングス・ファインダー2.0
トム・ラス, 古屋博子
日本経済新聞出版
感想
前提として、私はストレングス・ファインダーを受けていない。本書を図書館で借りたのだが、「付録無」とされており、本家で50$も支払うのは流石に躊躇われたからだ。私の思想として、お金はなるべく経験に変えたいというものがあるのだが、とはいえアンケート形式の診断のためだけに7,000円もの出費を支払うのは躊躇われる。したがって、以降の感想は診断を受けていない上での妄言となる。
といっても、本書を読んで感じたのは主に2つである。1)強味を把握することの重要性と2)性格診断の存在意義についてだ。
まず、1)強味を把握することの重要性についてだが、これは言うまでもなく大事である。ただ、それに係る印象的なエピソードが本書で取り上げられていたので、要約して挙げておく。というのも、聖ペテロは、史上最高の将軍が誰かと問われた際に、ただの労働者を指して「彼は史上最高の将軍だった。もし彼が将軍になっていたらね(p.29)」と答えるのである。
ベタと思えるほどのわかりやすさだが、一方で示唆に富んでいることも事実である。冒頭で「ゆりかごから職場まで、私たちは『強み』よりも『欠点』のためにより多くの時間を割いている。」と主張されるように、現代(2025)社会は、自身の欠点と否応なく向き合わされるようになっており、著者はその功罪を今一度問い直しているのだ。
個人的な所感としては、欠点の克服、あるいはそれに挑戦する姿勢自体が、人生により彩りを与えてくれるものだと思っているので、手放して著者に賛同はできない。ただその一方で、自身の強み/弱みを正確に把握することで、円滑な業務遂行に繋がることも事実だと思えるので、強味と弱みの両側面を自覚することが大事なのだと思う。月並みな表現になってしまうものの、自身の良さと課題を正確に把握することこそが、ビジネスの成否を分けることになるのだろう。
そして次に2)性格診断の存在意義である。単なるセレンディピティに過ぎないのだが、「性格診断ブームを問う(岩波書店)/ 小塩真司」という本が二日前に出版されている。当然私はその本を読んではいないのだが、なんとなく、本書にも通じるようなことが書いていそうなように思う。ストレングス・ファインダーも、性格診断の一種であり、そこには本書の言うような「功」のみならず、少なからず「罪」も存在していると思えるからだ。「性格診断ブームを問う」を読むことによって、より俯瞰的な視点から自己分析について考えるきっかけになるのではないのだろうか。
正直、本書は実際にストレングス・ファインダーを受けてこそ真価を発揮するように思う。34項目の特性は、診断を受けていなくても、業務上での協力をする際に役立つのだろう。とはいえ自分事として考えられない以上、どこか他人事で、真に迫るような実感はあまり持つことができなかった。ただ、流石に50$も払う余裕はないので、一旦岩波書店の新刊を読んで、それから改めて本書を読み返してみたいと思う。
余談
実は、この感想文、べろんべろんに酔っぱらいながら書いている。後日の私はどう感じるだろうか。酔っぱらっている身としては、(余談を除いて)それなりに普段通り書けていると思っているのだが、果たして……。
ちなみに吞んでいるのは「里山のめぐみ」という栃木県のワイン。先日、日光に行ってきた時のお土産として、今呑んでいる。粘性が低く、清澄度が高い割にはタンニンの渋みが強く、ベリーが入っているということもあり、中々独特な風味になっている。