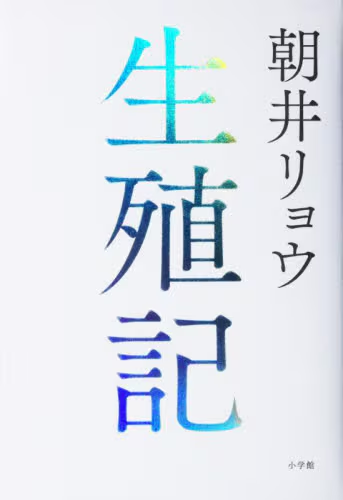感想
内容の良さでカバーできないほど、語りがキツイ……。あまりにも、あまりにも饒舌すぎて、読んでいて全く楽しくない。ペットの声をナレーターがわざとらしくぶりぶり吹き替えするような、虫唾の走るペット番組みたいである。本当に、「ですよね?」が多すぎて、黙れ!!!と叫びたくなる。読者の感情を、語りが勝手に代弁しないでくれ。
ただ、話自体は好きなんです。というか、ほとんど「小説(講談社)/野崎まど」の内海なのだから、好きにならないはずがない。生産性から降りたい尚成と、ひたすら読んでいたい(書きたくない)内海は、「好き」という原動力の違いこそあれど、生産性から切り離されたところで生きているという点で共通する。そして彼らは両者とも、物語を通して生産性を主軸に進む社会に擬態こそすれ、迎合は全く行わない。いわんやそこには圧倒的な肯定があり、私にとって垂涎物の世界が広がっている
…….はずなのに。生殖器がうるさすぎる。懇切丁寧な解説なんていらない。尚成がお菓子と運動のサイクルによって生きていることなんて、マカロンを作っているという一言だけでおおよそ想像がつくのに、だらだらと冗長に、さもとんでもない事実を発見したかのように語って、挙句の果ては「~ですよね?」と読者に同意を求めてくる。本当に、やかましい。一旦黙ってくれ。お前がいなくても、私は尚成の人生を拝読するから。
まあ、ポジティブに深読みをするなら、男性器って割とそういうもんなので仕方ない気もする。余計なときに活動しようとはりきったり、自身の思考とは別に勝手に突き進んだり、落ち着いてくれ……としばしば願ってしまう代物である。そういう、男性器のうざさを表現して、あえて語りすぎているのだとしたら、朝井リョウ氏の完全勝利であり、私の完敗である。
自分で「完敗」と書けるくらいには負けを認めていないのだけれども、とはいえ直木賞を若くして取れるレベルの作家ならここまで考えて当然のようにも思えてしまうから悔しい。黙れ黙れと読書中終始不快になっていた私は、あくまで朝井リョウ氏の手のひらの上で踊らされていたのかもしれない。悔しい。
とはいえ、とはいえ。本書の「語り」を面白いとは一度も思えなかったのは事実である。何回も書いた通り、内容は頗る良かったのだが、語りだけは本当に好きになれない。私は我儘な読者なので、どれだけ不快な話だろうと、文章表現としての面白さを求めてしまう。「四隣人の食卓(書肆侃侃房)/ ク・ビョンモ」なんかは、内容の不快さに反して一気読みしてしまう面白さで、それは文章そのものに読ませてくれる良さがあるからだろう。本作に対しても、そうした文章としての楽しさを味わいたかったのである。
余談
セルフエコーチェンバーを恐れずに書くと、たぶん私は「お上手」な作家さんがあまり好きではないのだろう。伊予原新氏とか、安野ただひろ氏とか、レティシア・コロンバニ氏とか。マルチな能力があって、「ツボ」や「コツ」を百発百中ばっちり抑えられるような人。そういうのを読むと、どうも過度にお節介を焼かれているようで、うざい!と感じるのだろう。
別に私がそういう好みを持つこと自体は、なんにも問題ないのだが、こういうタイプには得てしてファンが多いから、迂闊なことを言えなくて困る。読書会って、当然「好き!」を語り合う場なんだけれども、ごくごくたま~~~に「無理!」を語る会があってもいいんじゃないかなあって、思ったり、思わなかったり。
さらに余談
余談を書ききって思ったのだが、これ、中々変ではないだろうか。というのも、小説の好みと対人関係での好みが正反対なのだ。小説は上述の通り、語りすぎず、多少不器用な、そして熱量のある作品が小綺麗な作品よりも好きである。一方で、対人関係ではむしろ遠まわしな言い方を忌避する傾向にある。極端だが、どちらかと言えば「はっきり言え!」タイプなのである。
文字メディアとバーバルコミュニケーション、性質が違うのだから好みも異なるのは当然っちゃ当然である。でも、それにしたって乖離しすぎじゃないだろうかとも感じる。一体これは、なんなのだろうか(オチ無、未解決)。