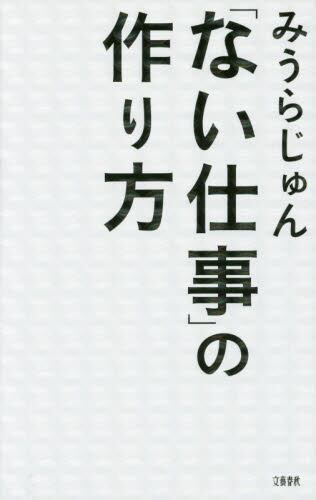感想
最近の読書のおかげで、読み味が深まったので、本そのものとは別に楽しめた一冊だった。というのも、私はみうらじゅん氏のことを全く知らないが、本書を読み始めてからず~っと、以前読んだ「ビックリハウス」世代みたいな言動だなあと思っていた。したらばp.118でビックリハウスに漫画を掲載した話が登場し、答え合わせをした感覚になった。しかもその後糸井重里と共同で漫画製作をするというおまけつき。もう、全てのピースがぴったりはまってとにかく気持ちよかった。
さて、個人的な読書体験の話はここまでにして、本書の内容について触れていく。本書は、みうらじゅん氏がいかにして名前付け・ジャンル分けされていないコンテンツを発掘するかを、本人が語っていく内容である。「嫌だと思えるほどのものを、どうやったら好きになれるか」考えたり、「一人電通」と称して出版各社へ接待をするなど、仕掛け人としての思想がふんだんに語られていて、クリエイターにとっては概ね参考になると思われる内容だった。
一方で、彼の思想は、令和七年の現代ではそっくりそのまま同意することのできない部分も多々あった。例えば彼は、ある特定の何かの面白さを伝えたいとは思うが、一大ブームになった後でそれがどのような変遷を辿るのかは関知するところではないと述べている。消費社会の寵児のような思想であり、正直これには無責任と思わずにはいられない。当人の興味の有無を問わず、外部の人間が特定の文化をコンテンツとして消費社会に引っ張りだした以上は、相応の責任を求められるのが筋ではないだろうか。みうらじゅん氏に関しては、結果的に上手くいっている(ように見える)から良いものの、社会の分断や軋轢にも繋がりかねない気がして、どうにも冷や冷やするのだ。
他にも「ブーム」や「プレイ」などを語尾につけると言葉が軽くポップになるという主張もあり、これもまたその功罪が問われるように感じられる。確かに、一例として取り上げられる「親孝行プレイ」は、社会の親子関係の良好化に貢献していて、素晴らしい行いのように思える(そもそも親子関係を良くすることが良いことなのかという議論は一旦置いておくものとする)。しかし、ブームやプレイという形で言葉を軽くすることによって、取りこぼしてしまうものはないだろうか。「スマートシティはなぜ失敗するのか」で語られるような、ダッシュボード的世界観を促進しているようでもあり、臆面もなく首肯できるかというと、なんとも難しい話である。
以上を踏まえると、みうらじゅんという人間は、功罪という平均台の上を奇跡的なバランス感覚で踊っているように思える。一歩間違えれば大炎上し、誰かを傷つけかねないにも関わらず、今のところ飄々と面白いコンテンツを生み出し続けている。一世を風靡した糸井重里でさえTwitterでぼこぼこに叩かれているというのだから、彼のバランス感覚は中々のものだと思う。
もしかするとそこには、「母親が嫌がりそうなことだけはやらな」いという彼の信条が影響しているのかもしれない。彼の母親の倫理観に頼っているという点で危うくはあるものの、彼のコンテンツの在り方に大きく影響していることは間違いない。「母親」という具体的なロールモデルがいることによって、軸のある活動ができているのだろう。(不倫してたらしいけど……)
以上、本書は最近の読書遍歴の中で読むことで、より考えが深まる一冊だった。仕事へのマインドとして見習いたい部分が多くある一方で、やるだけやってあとは知~らないという無責任さのないよう心掛けたい。