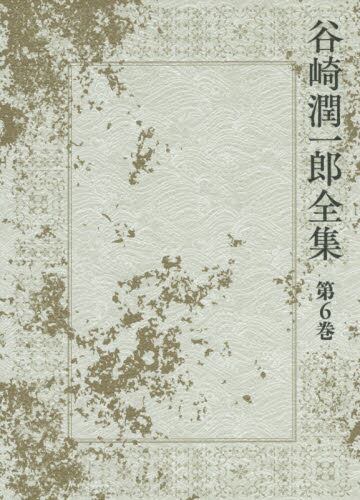感想
再読しても新鮮に味わえる幻想的な風景が、胸に沁み入る。……単に前回読んだときのことを忘れてるだけなんだけど。
冗談はさておき、描写力の高さは折り紙付きである。正直、前期の谷崎は荒削りで洗練や柔らかさとは少し縁遠いと思っていた。カタカナ言葉も利用するし、名を轟かせた一因である耽美的な要素が全面に出ているものだと思いこんでいたのだ。
ところがどっこい、そんな偏見は容易く吹き飛ばされる。月明かりに照らされる海辺をただひたすは歩くだけなのにぐんぐんと引き込まれてゆく。最近読んだ「ケアと編集」の言葉を借りるなら、谷崎の幻覚を一緒になって観ているような心持ちになる。夜という寂しさと、月明かりの真っ白な不安が入り混じり、母という幻想を立ち上らせる筆致はもう、圧巻の一言に尽きる。
そもそも、この作品にはこれといった展開がないのである。夜道を歩き、若かりし頃の母と出会い、抱擁を交わす。ただそれだけなのに、どうしてこうも引き込まれるのか。どうして涙が零れそうになるのだろうか。わからない。全くもってわからないのだけれども、彼の切な想いが、胸に深く、深く喰い込むのである。
ただ一方で、「母恋ふる記」にあるのは、愛なのだろうか。母というよりも、母性を求めていたに過ぎないような気もする。途中、小母さんのことを、お姉さんと呼びたがっていたように、彼は母という存在以上に、自身を無条件に守ってくれる母性を欲していたのではないだろうか。
ここには、谷崎が長男であったということも重要な要素となる。長男は、兄弟姉妹の責任を一手に引き受ける存在である。望むと望まざるに関わらず、年端もいかないうちから大人として扱われるのである。そこには、誰かの面倒を見るばかりで、面倒を見られるという経験が明らかに欠如しており、ゆえに姉を、母を、庇護者を求めるのである。(ソース: 私)
本作で、そうした欠如が解決されることはない。それに、本作のような背景があるからといって、後の小田原事件が許されるわけでもない。この作品で大事なのは、作品が何かを目的に作られていないということである。作品そのものが目的であり、要は彼なりのデトックスに他ならない。勝手な想像だが、執筆という営みそのものに、母という存在への対処が組み込まれているのではないだろうか。
だからこそ、本作は物語的な展開がなくても良いのである。宛もなく歩くことそのものが目的であり、その時々の幻想こそが何よりも重要なのである。あれ、これってもしかして、ケア? (ほんと、最近目に入るものすべてがケアに見えて仕方がない。)
本作は、「読んでどう感じるか」という作品ではない。「読むこと」そのものが、大事なのである。谷崎は書き、私は読む。その間にだけ開かれる世界が、確固として存在しているのである。