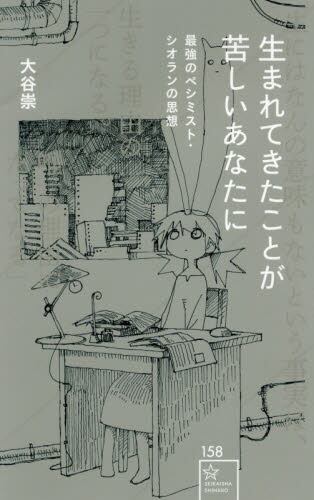感想
主張自体は私にとって良いはずなのに、本書はあまり面白くなかった。
まず、原典を読めば良いと思ってしまった。本書はシオランの解説書だが、正直なところ、納得のいく箇所は解説無で納得できるし、納得できないところは解説されても納得できない。色々とかみ砕いてわかりやすくしようとしてくれている努力は伝わるものの、かみ砕かれる前の原典自体がそれほど読解困難な内容ではないから、むしろ解説自体がノイズになっているようにも感じてしまった。
それから、主張が300頁を越えてもほとんど変わらず、飽きてくる。結局は、ペシミズム・反出生主義である。思考プロセスに紆余曲折はあるのだけれども、最終的には「どうせ死ぬのだから」という話に落ち着く。もちろんその話自体は、社会圧に晒されて生きづらさを感じる現代人にとって救いにはなるのだけれども、本として読む分には展開が変わらず平坦でつまらない。
とはいえ好きな言葉もある。一昨日読んだ「惑星語書店/キム・チョヨプ(早川書房)」でも取り上げたが、「笑いは生と死にたいする唯一の、まぎれもない勝利だよ」という言葉はかなり印象に残っている。途方もなくペシミスティックにものを考える人間が、笑いを勝利と考えているのである。なんとなく、「笑い」に宿る圧倒的なパワーを感じられて、すごく元気になれる一言である。
最後に併読本を二冊挙げて感想文を〆る。というのも本書は、心のセーフティネットとしてそうした考えを持っておくことは良いのだけれども、それに傾倒しすぎると取りこぼしてしまうものがあるように思えてならないのである。シオランに言わせれば、そういう取りこぼすものそのものも無意味なのだろうけれども、読書会に行くような人間である私としては、流石にまだ解脱したくはない。たくさんの人とお話をして、たくさんの人と笑い合いたいのだ。
そんなわけで、まずは「「むなしさ」の味わい方/きたやまおさむ(岩波新書)」を挙げる。むなしさに打ちひしがれて何もできなくなってしまうことが、良く作用するときもあれば悪く作用するときもある。前者であればシオランを読んで解脱すれば良いのだけれども、後者ならばこれを読んで、むなしさを「味わって」みることが大事だろう。むなしさを味わい、結果的にそれが自身の養分になることで、解脱でなく、人間として、再び立ち上がることができるのではないだろうか。
そして「むなしさ」へのもう一つの対処が「客観性の落とし穴/村上靖彦(ちくまプリマー新書)」に書かれている。それは、「『にもかかわらずある』を語ろうとすること」である。シオラン的にはそう考えるものまた「むなしい」のだろうし、本当に苦しいときはそれでいいだろうけれども、当人の中に一抹でも生への執着があるならば、この「にもかかわらずある」こそが助けになってくれるのではないだろうか。
以上、人生の奥の手として心に秘めておきたいけれども、常用的に摂取するのは憚られる感じの一冊でした。(つくみず先生の絵は毎日眺めたいです)