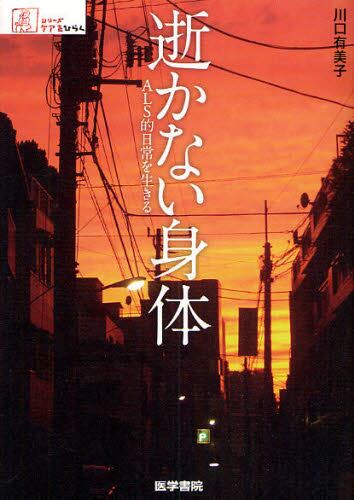感想
自分が伝えたいことの内容も意味も、他者の受け取り方に委ねてしまうー。このようなコミュニケーションの延長線上に、まったく意思伝達ができなくなるといわれるTLSの世界が広がっている。コミュニケーションができるときと、できなくなったときとの状況が地続きに見えているからこそ、橋本さんは「TLSなんか怖くない」と言えるのだ。
p.211 第3章 発信から受信へ
上記の通り、橋本氏がコミュニケーションの可否の世界を地続きに見ているように、本書はALSとそうでない人の世界を地続きに見ている。両者の間には大きな違いと、それに伴う壁があるように見えるが、実際はそうでなく、幾重にも渡る「できなくなる」を繰り返して辿り着く連続的なものなのである。
先日参加した、著者と上野千鶴子氏の対談イベントでも触れられていたが、健康な人はどうしても、「自分が何かできなくなる」状況に想いを馳せることが難しく、ゆえに自分がそうなったときにその現実を受け入れられなくなってしまう。本書でもたびたび著者がALSの母を「楽にさせてあげたい」と述懐しているが、そう思う原因の一つには、「母の元気な姿」が脳裏に残っていることが挙げられる。
つまり、結局のところ「心のもちよう」なのだ。結論だけ切り取ると陳腐に思えてしまうが、これを実現するのは中々に難しい。著者でさえ、長い歳月を苦しみとともに過ごすことでようやっと受け入れられるようになったわけで、おそらく私も、実際にその状況にならないと本当の覚悟を持つことは難しいのだと思う。
とはいえ、渦中の「ケアする/される人」の経験を本という形で読めるのはすごく貴重なことで、「できなくなること」への抵抗が少しなくなったような気がするし、そう思うことで心がふっと軽くなったようにも思える。成長至上主義に侵された精神が、ゆっくりと解毒されていくようである。
それから他にも思うところはある。それは、看護師・介護士の難しさである。(正直うろ覚えなのだが)「感情と看護(医学書院)」では、当事者の身に「なる」ことがケアする上で大事なのだが、それゆえに、当事者と同期しすぎることで自身との境界線が曖昧になり、精神的に苦しくなってしまうこともあるのだ。
上記を踏まえて、ALSの介護を考えてみると、色々な想いが渦巻く。先ほど私は「心のもちよう」と書いたけれども、とはいえケア「する」ときの自分は、ケアすることが「できる」側に立っているという意識が、たとえ無意識だろうと少なからずある。そこから、「できなくなる」という存在に同期していくのは、相当に大変なことだろうことは想像に難くない。
だから何?と言われてしまえばそれまでなのだが、看護師・介護士の方々の苦労を思うと、畏敬の念が湧いてくる。読書会でコミュニケーションのいろはを学んでいる私からすると、ケアというのは、本当に、難しいことなのだと思い知るばかりで、まだまだ道程は長いのだなあと、感じ入るばかりである。
メモ
本記事にビックリハウスとタグ付けしているのは、p.189で川口氏が自身の世代やその前後の世代の温度感を書いているため。