感想
保育園へ娘たちを迎えに行く時、川の近くで、吹雪の中にオオカミが見えた。日本のオオカミはいつ日本から消えたのか、という本を図書館の本棚で見たけれど、絵本と妖精の本を借りた。オオカミの本を借りればよかった。
p.170 冬至
知らない間にまた朝になってそば茶を飲んでいる私がいた。一瞬しか経っていないのに、気づかないうちに窓に置いたカリンが腐った。早めにジャムにすればよかった。悪いことをした。ルーマニアの家でもよく窓においてあった。冬の寒い日に薪ストーブの上に置いて、焼いたらごちそうだった。
パンは発酵してはみ出しそう。焼く準備。あ、娘たちの迎え。雪かき。オオカミの本を借りればよかった。何年もここに住んでいるが、はじめてオオカミを見た。幻のだ。「日本ではオオカミは神様だよ」と、夫は言った。
イリナ・グリゴレ氏の文章は、とにかく油断できない。彼女の人生の断片が、モンタージュのように切り貼りされて、目まぐるしくその景色が切り替わる。きっと、彼女にとってはそう繋ぐのが最適なのだろうけれども、「イリナ・グリゴレ」という人間を全く知らない私にとっては猛吹雪の中を歩く感覚に近く、ぼんやり読んでいると自分が今どこにいるのかが全くわからなくなってしまう。
ただ、読んでいくうちに少しずつ「イリナ・グリゴレ」という人間が輪郭を持ち、立体的になっていくのだから面白い。一般的な小説が、あるゴールに向けて(多少寄り道しつつも)概ね一直線に掘っていくものだとしたら、本書は様々な場所を少しずつ掘っていき、読み終えたときにようやっとそれぞれの穴が地下奥深くでかろうじて繋がるといった感じである。だから、最初は頗る読みづらいのだけれども、読み進めるうちに、味わったことのない面白さがじんわりとやって来るのである。
ここで思い出すのは、イリナ・グリゴレ氏がTwitterのbioに「カテゴライズされたくない」と記載していた時期があるということである。文化人類学者、ルーマニア出身、女性など、わかりやすくカテゴライズすることはいくらでもできてしまう。しかし、彼女はそれを拒否し、「イリナ・グリゴレ」としての存在を文章に落とし込んでいるのだ。ゆえに、オオカミも雪国もカリンも青森も全てが必要であるし、だからこそカテゴライズの隙間に零れ落ちるものも拾いきった景色を描出ことができるのだろう。
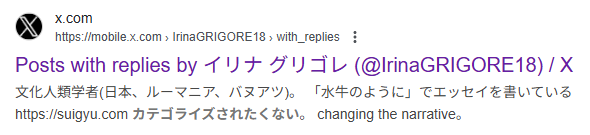
どうやら今はbioから消されたらしく、検索エンジンからでしか確認できなかった
転じて、感想を書くのが難しくもある。カテゴライズされた作品ならば、そのカテゴリを基準にして語れば良いが、こと本書ではそれができない。あくまで本書そのものが基準であり、何物とも比較させない、個としての力強さがある。それが魅力でもあるのだけれど、例えば「力強い一冊」なんて語るだけでは足りない。真っ当な感想文を書くならば、本書と同じくらいの文量を書かなければならないのだと思わされる。
流石にそれはやらない(次作の「みえないもの」も読みたいし)。だからこそ、私は本書をわかった気になってはいけない。いや、どの作品に対しても理解した気になるのは良くないのだけれども、忘れがちな言説が、本書によって思い起こされたのである。
いや~、これ、すごい。
