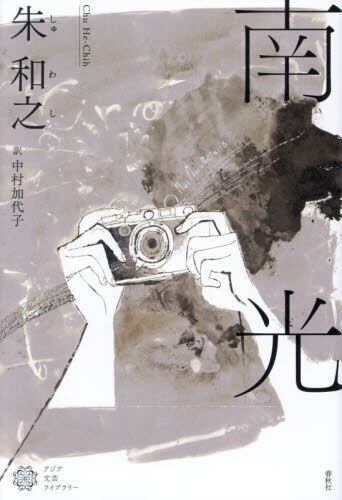感想
小説として、相当つまらなかった。というのも、第三章「女の顔」では、鄧南光の妻「藩清妹」の視点で彼について語られるのだが、写真にばかり熱を上げて家庭を顧みない彼に辟易し、完全に心を閉ざす様子が描かれている。「少なくとも、私はあなたのコレクションのひとつにはならないわ」と発露する藩清妹の心情からは、鄧南光が「月と六ペンス」のストリックランドのような芸術家であることが伺える。
そんな描写の後に、どれだけ写真への想いを熱量をもって語られても、正直冷める。自分の好きなことばかり打ち込んで、周りのことは一切気にせず不幸にしている。そんな人間の物語を読んでも、果たして感動することはできない。情動へ訴えかける作品として書くならば、いっそのこと藩清妹の描写は削ってほしかった。例えば映画「Whiplash」ではニーマンとフレッチャーの閉じられた世界に焦点が当てられていたように、本作においても、中途半端に余所見をせず、鄧南光にもっとフォーカスを当ててほしかったように思う。
一方で、鄧南光の写真集「凝望鄧南光 観景窓下的優游詩人1924~1945」のタイトルで、「ダニエル・ブラッシュ」を思い出す。というのも、写真集のタイトルの日本語訳が「鄧南光に目を凝らす ファインダーの吟遊詩人1924~1945」とされており、ダニエル・ブラッシュの発した「I wanted to do a poetry book, a visual poetry book.」という言葉と共鳴するように思えるからだ。
つまり、鄧南光は写真という成果物を生み出したのでなく、写真という表現手法を通して「詩」を生み出していたと解釈されているのだ。この視点は、Google Pixcelでパシャパシャ気軽に写真を撮る私の感覚にとっては新鮮で面白い。写真は、ファインダーに映る景色をそのまま写しつつも、その枠内外で取り上げられるもの/取りこぼされるものが確実に峻別されてしまう。そこに想いを馳せることによって、ただの画像から、様々な感情や情動がパッキングされた「詩としての写真」が生まれるのだろう。
そういう意味で、鄧南光はやはり時代の寵児なのだろう。著者や訳者を始めとして、見た人に何かを残す写真を撮るというのは、誰でもできるようなことではなく、彼の功績は確固として存在することは理解できる。とはいえその背景には、鄧南光の画角からはみ出て、最後まで取り上げられることのなかった「藩清妹」という存在がいて、手放しに賞賛できる人物でないということも心に留めておきたい。